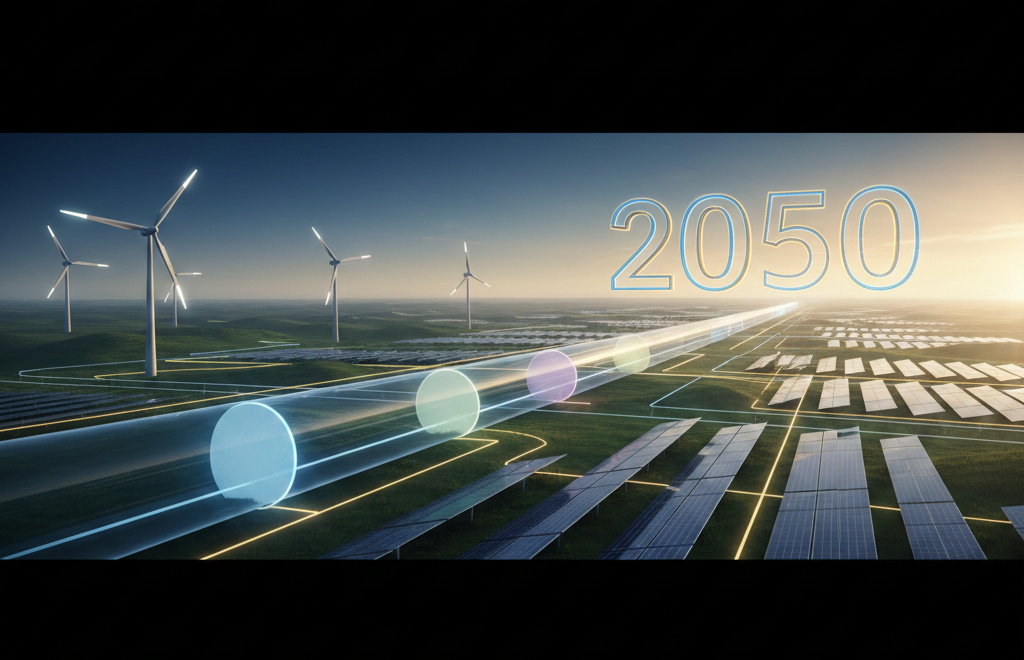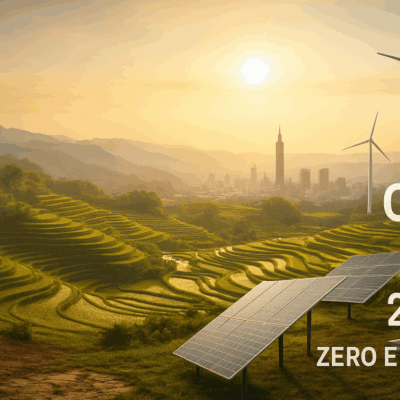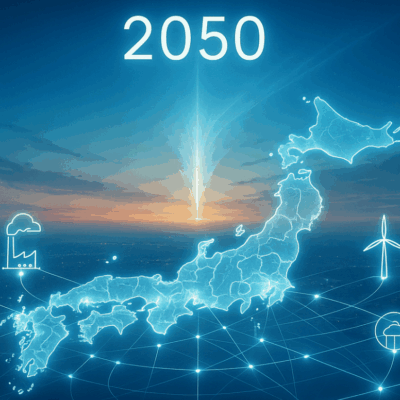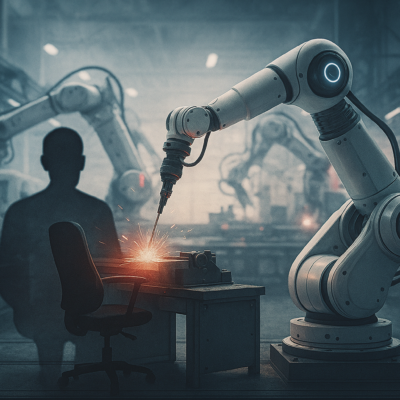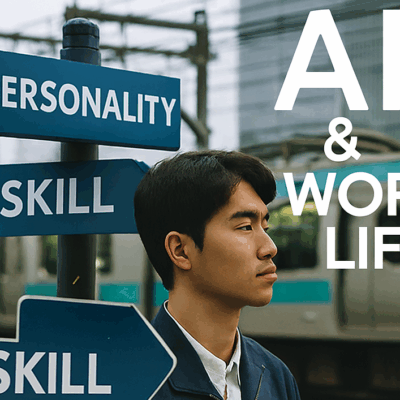社会的共用資本としての送配電網:市場原理を超えた国有化と「シンMMT」新財源モデル
4.まとめと「シン送配電網2050」実現への提言
1)本稿が提起した構造的矛盾の解消
本稿は、送配電網が直面する構造的な矛盾、すなわち「脱炭素化・経済安保に不可欠な自然独占インフラであるにもかかわらず、巨額の投資リスクを市場原理に委ねている」という問題を起点に議論を進めてきました。
現在の電力システムでは、公的資金の投入という形で既に国民がリスクを負担し始めているにもかかわらず、その所有権とガバナンスが民間企業に留まっているという、極めて不透明かつ不安定な状態にあります。
第3章で提案した「送配電網の社会的共用資本化と国有化」は、この構造的矛盾を解消し、電力システムを真に「公益の最大化・最適化」に資する基盤へと変革するための、不可避・必須の選択であると考えます。
2)「シンMMT」による新財源モデルの可能性
この変革の成否を握るのは、国有化によって生じる「買収費用、投資費用、運営費用」を賄うための財源の確保です。従来の財政枠組みに頼るのではなく、本稿では「シンMMT的な発想」に基づく「特別財源方式」を提案いたしました。
このモデルの中核をなす「共用資本専用通貨」は、以下の二重の目的を達成するための、革新的な手段となります。
・インフラ投資の加速: 通貨の利用使途を国内の資材・人件費に限定し、利用期限を設けることで、資金が送配電網の強化に迅速かつ確実に循環し、国内サプライチェーンの強靭化に直結します。
・インフレ抑制: 通貨の目的と使途を限定し、法定通貨の信用から切り離すことで、公的な必要性に基づく投資を、既存経済への過剰な流動性注入(インフレ)リスクを抑えながら実行することが可能となります。
この特別財源方式は、ベーシック・ペンション構想における「限定デジタル通貨」の設計思想を参照したものであり、「公的必需品の調達・投資」に特化した新しい金融・財政政策のあり方を探る、「シンMMT2050の適用研究考察対象」となります。
3)「シン送配電網2050」実現に向けた段階的ロードマップ
送配電網の社会的共用資本化は、制度・法制・金融システム全域に及ぶ社会変革であり、2050年の完全実現を目標とする段階的な移行戦略が必要です。
最初の5年間を理念の浸透と合意形成に充て、全5フェーズに分けて推進する構想です。
| フェーズ | 期間 | 主要な目的と行動 |
| 準備フェーズ1 | 2026年~2030年 | 理念と構想の理解浸透のための期間 |
| * 社会的な議論と合意形成: 国有化と新財源モデル(共用資本専用通貨)の必要性、効果、仕組みを広く啓発し、社会的な議論と理解浸透を図ります。* 基礎調査: 送配電資産の正確な時価評価、買収費用の試算を実施します。 | ||
| フェーズ2 | 2031年~2035年 | 法制化検討と新財源方式の検討、それらの合意形成 |
| * 法的基盤の検討: 「送配電網特別会計法」の骨子、日銀との連携に関する法制度(日銀法等)改正案の検討と、国会での合意形成を最優先で進めます。* 新財源の検討と承認: 「共用資本専用通貨」の具体的な発行・管理ルール、および換金・回収の仕組みの詳細設計を完了させ、関係省庁・日銀との最終的な承認を得ます。 | ||
| フェーズ3 | 2036年~2040年 | 国有化着手と新財源方式による運営及び管理着手と同中長期計画策定 |
| * 国有化の着手: 法的基盤に基づき、優先領域(連系線、基幹系統等)から国による資産買収に着手します。 新財源方式の運用開始: 買収領域に対し、「共用資本専用通貨」による運営・投資費用の支給を開始し、新財源方式の実務的な運用を確立させます。* 中長期計画の策定: 2041年以降の国有化完了に向けた技術・投資・運営に関する中長期計画*を策定します。 | ||
| フェーズ4 | 2041年~2045年 | 第1次国有化完了と同運営管理方式軌道化・必要調整実施 |
| * 第1次国有化の完了: すべての一般送配電事業者からの資産買収を完了させ、国の非営利機関への運営委託体制への移行を完了します。* 運営管理の軌道化: 「共用資本専用通貨」による財源方式を完全に軌道に乗せ、運営上の課題を解決し、安定供給体制を確立します。* 料金体系の調整: 新財源方式の貢献度を評価し、系統利用料金の抜本的な低減化に着手します。 | ||
| フェーズ5 | 2046年~2050年 | 第2次国有化完了(全完了)と次期(21世紀下期)長期計画策定 |
| * 第2次国有化の完了(全完了): 買収した資産の法的な整理・統合を含め、送配電網の社会的共用資本化を完全に完了させます。* 長期目標の達成: 共用資本専用通貨による維持・運営費の全額賄いを実現し、利用基本料の無料化を達成します。* 次期長期計画の策定: 21世紀下期を見据えた、エネルギー・デモクラシーと革新技術導入を柱とする次期長期計画を策定します。 |
4)最後に|「シン日本社会2050」の基礎インフラとして
繰り返しになりますが、送配電網の社会的共用資本化は、単にエネルギー政策の一環に留まるものではありません。
それは、「シン循環型社会2050」のエネルギー自国自給自足の基盤であり、「シン安保2050」を支える社会経済安全保障の生命線です。
この実現により、市場原理から解放された強靭で透明性の高い送配電網は、国民の生存権と経済活動を支える確固たる基礎インフラとして機能し、ONOLOGUE2050が想いを致す「少しずつ、よくなる社会」としての「シン日本社会2050」の構築に不可欠な要素となるでしょう。
またその実現は、グローバル社会のモデル事業としても認知・推奨され、シン・グローバル社会2050の範の一つとなると考えています。
なお、本稿でテーマとした「送配電網」の社会的共用資本化やシンMMTの適用対象化は、一つの「とっかかり」としての意味をもちます。
すなわち、これから同様の視点や政策・対策を推奨する具体的な事案・案件を取り上げていくことも、当サイトの目標・目的でもあります。
息の長い、なにしろ2050年をめざしてのことですので、宜しくご理解とお付き合いをお願いします。