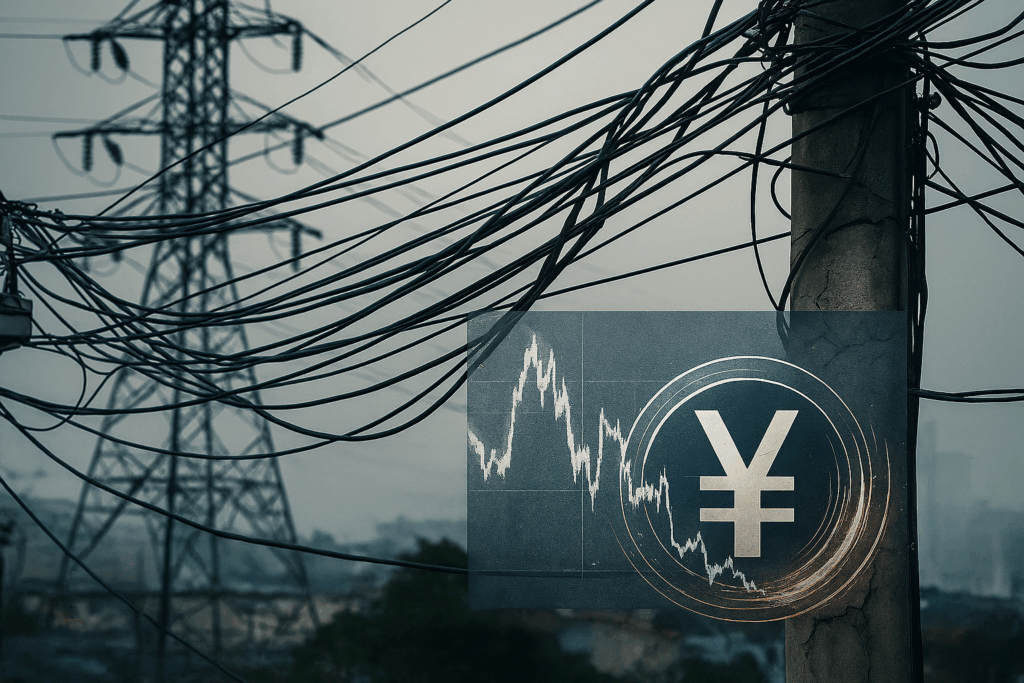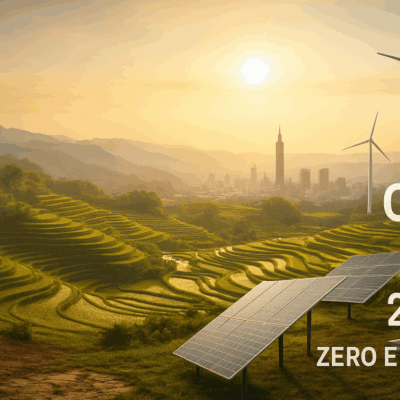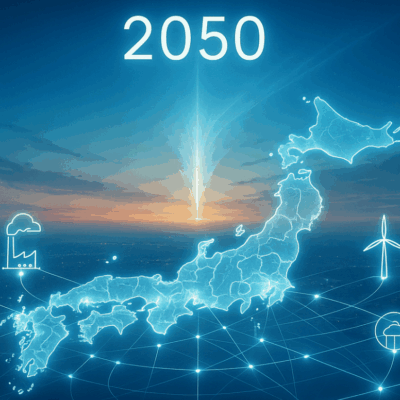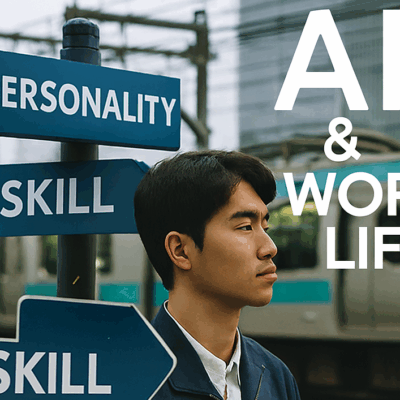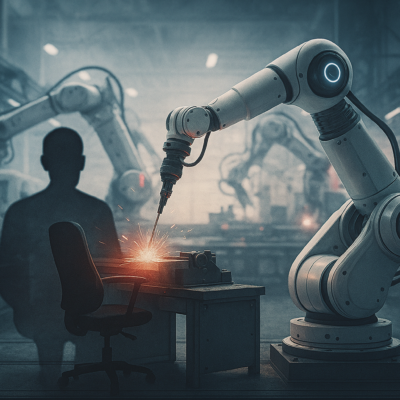社会的共用資本としての送配電網:市場原理を超えた国有化と「シンMMT」新財源モデル
はじめに
シン循環型社会2050、シン安保2050、そしてシン社会的共通資本2050に関わる具体的な課題の代表がエネルギー・資源問題である。
その軸となる考え方はエネルギー及び資源の「自国内自給自足」にある。
今回は、直接的なエネルギー・資源・環境問題に焦点を当てるのではなく、それを支えるインフラの一つに焦点を当てたい。
2025年11月11日付日経に「原発・送配電に公的融資 電力確保、脱炭素促す 政府先導で長期資金」というテーマの記事が掲載された。
⇒ 原発・送配電に公的融資 電力確保、脱炭素促す 政府先導で長期資金 – 日本経済新聞 2025/11/11
続いて、同月23日に「東電子会社に外部資本 送配電など、収益改善めざす再建計画、国と協議」というテーマの記事が。
⇒ 東電子会社に外部資本 送配電など、収益改善めざす 再建計画、国と協議 – 日本経済新聞 2025/11/23
どちらも、東電への投融資問題を取り上げたもの。
その対象となる事業が、原発、再生エネ、脱炭素、小売り、そして送配電網など。
どのテーマも、資源・エネルギー戦略課題だが、今回はその中の「送配電網」を取り上げたい。
(参考)以下の関連記事もある。
⇒ 北海道ー本州の海底送電線に公的保証案 1.8兆円事業、民間融資誘う – 日本経済新聞 2025/5/29
1.【背景】日経新聞記事が示す送配電網の現状と課題
まず、上記2つの記事を簡単に要約しておきたい。
1)大手電力の送配電網に関する日経主要2記事の要約
政府および東京電力をめぐる最近の報道は、以下の2点に集約される。
記事①「原発・送配電に公的融資」
電力確保と脱炭素の両立に向けて、政府は原発・再エネ・送配電網投資に公的機関による長期融資の仕組みを導入する方針を固めた。
16年の電力全面自由化以降、電力会社は投資回収の不確実性増大により資金調達が困難化している。
AIデータセンター向けの需要増加など、電力需要の拡大も見込まれ、2050年カーボンニュートラルの実現には180兆円規模の投資が必要とされる。
政府の信用力を活用し、民間との協調融資により、脱炭素電源と送電網投資を加速させる狙いがある。
記事②「東電子会社に外部資本」
東京電力HDは送配電、小売り、再エネ事業子会社に民間資本の受け入れを検討している。
福島第一原発事故対応に伴う巨額負担(総額17兆円)、設備投資増大、AI普及による追加投資などにより、
7期連続のFCF(フリーキャッシュフロー)赤字という厳しい財務状況にあるためだ。
再建計画「総特」第5次案では、外部資本を呼び込み、収益性回復と電力インフラ強化を図る方針が示されている。
ただし、原子力リスクへの懸念から、出資実現には不透明感も残る。
2つの記事の要点を以下に一覧化した。
| 記事 | テーマの概要 | 資金調達の課題 | 目的・焦点 |
| 記事1(2025/11/11) | 原発・送配電への公的融資 | 電力自由化後の投資回収見通しの不確実性、金利上昇に伴う民間融資・社債のコスト増。 | 脱炭素の実現(50年までに180兆円投資試算)、電力確保、長期的な資金調達の円滑化。 |
| 記事2(2025/11/23) | 東電子会社への外部資本導入 | 福島事故対応費用、設備投資(原発安全対策、送配電網増強など)による資金流出、FCFの連続マイナス。 | 財務体質の改善、廃炉費用拠出のための収益力向上、外部の資金・知見を活用した国内エネルギー基盤の強化。 |
◎両記事に共通する背景
→「電力自由化」「巨額投資」「脱炭素と経済安全保障」の狭間で、
安定供給の基盤としての送配電網再構築が急務となっている点にある。
2)送配電網の現状に関する記述整理
実際の記事において「送配電網」に関する記述部分は僅かだが、焦点を絞って以下整理してみた。
| 記事 | 送配電網に関する記述 |
| 記事1 | * 脱炭素電源(原発、再エネ)や送配電網への巨額投資に対し、公的融資を可能とする法改正を目指す。 |
| * 脱炭素実現のため、電力各社は送電網の増強を進める方針。 | |
| * AI開発に必要なデータセンター向けの送電など、電力需要増(今後10年で6%増)が見込まれ、送配電網の増強の必要性が高まっている。 | |
| 記事2 | * 東電HDの再建計画において、送配電の東電パワーグリッド(PG) への外部出資を募る。 |
| * 東電HDは、原発の安全対策や送配電設備への投資で資金の流出が続く。 | |
| * AIの発達による電力需要増で送配電網の増強など予想外の支出もあり、支出を抑える手立てが減っている。 |
この両記事において共通点として示されるポイントは以下のようになる。
① 送配電投資の必要性が高まっている
・再生エネ・原発の導入拡大には広域送電網の整備が不可欠である。
・AIデータセンター向けなど、新たな電力需要が増加している。
・北海道―本州間海底送電線など、地域間融通の強化が求められる。
② 投資回収の不確実性、資金調達の困難性が課題
・電力自由化後は、電気料金に投資回収を反映しづらい。(投資回収リスク)
・金利上昇により、融資・社債調達のコストが増加している。
・廃炉費用・安全投資が重く、財務改善が遅れている。
・財務状況から、民間資金だけでは賄いきれず、公的融資(記事1) や外部資本導入(記事2) という、政府・国の関与を前提とした資金供給策が模索されている。
③ 公的資金・外部資本が必要に|巨額・長期投資対象としても
・脱炭素化(再エネ大量導入)と電力需要増(AI、データセンター)対応のための数兆円規模の長期資金が必要である。
・政府の信用力を活用した、協調融資の仕組みが検討されている。
・東電は、送配電・小売り事業子会社への出資受け入れを模索。
・ただし、原子力リスクが出資判断の障壁となっている。
以上に加え、本稿として感じた点を、以下に付け加えてみた。
④ 社会基盤としての重要性、公共性の再評価が進む
・デジタル産業成長の基盤として、経済安全保障上も重要。
・エネルギー自給率向上のため、政策的な強化が求められる。
・電力の安定供給、産業競争力の維持(記事2)、脱炭素目標の達成(記事1)のいずれにおいても、不可欠な社会インフラとして送配電網の機能強化が不可欠な基盤となっている。