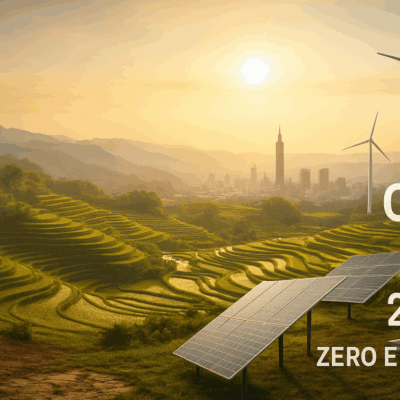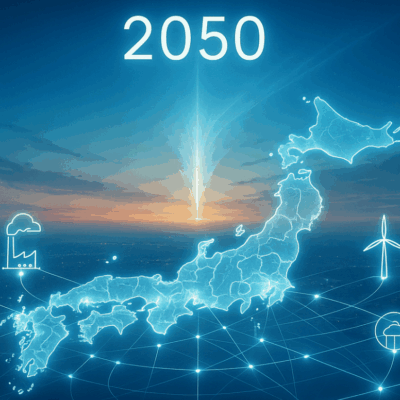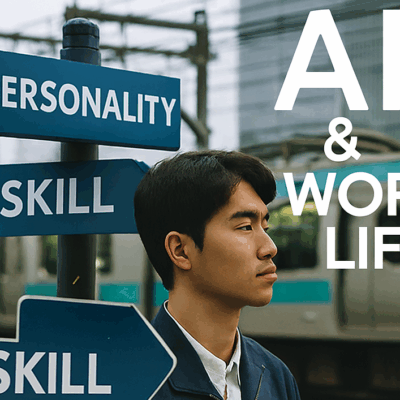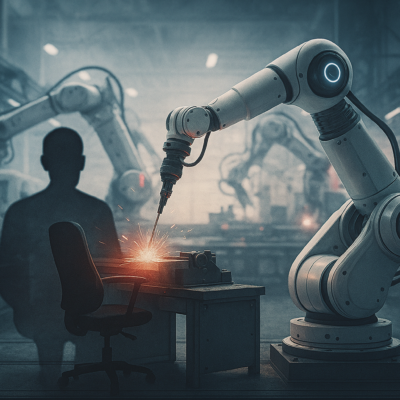社会的共用資本としての送配電網:市場原理を超えた国有化と「シンMMT」新財源モデル
3.社会的共通資本・社会的共用資本としての送配電網のあり方
第2章で確認した通り、送配電網は「自然独占」の特性を持ち、脱炭素化、経済安全保障、産業競争力の維持といった国家戦略の根幹をなすインフラです。
しかし、現在の電力自由化後の市場メカニズムでは、長期・巨額のリスクを民間だけで負いきれず、必要な投資が滞り、結果として公的資金の投入が不可避な状況に陥っています。
言い換えれば、「自然独占性を持つ巨大インフラ」でありながら、市場自由化のもとで投資リスクが企業に押し付けられているという、ねじれた構造の中に置かれている。
その状態を是正しようという動きが、ここまでで確認できたわけです。
そこで、この構造的矛盾を解消し、真に持続可能な電力インフラを構築するため、私たちは経済学者・宇沢弘文氏が提唱した「社会的共通資本」(Social Common Capital)の概念に基づき、「社会的共用資本」(Social Utility Capital)として、送配電網のあり方を根本から見直すことを提案します。
送配電網を国民のための社会的共用資本としてどう位置づけ、どう運営管理し直すか。
その制度設計の方向性を考え、構想・構築する作業となります。
1)社会的共通資本・共用資本としての送配電網の国有化を
送配電網が真の公共財として、国全体の持続的な発展に貢献するためには、現在の民間主導の枠組みから脱却し、社会的共用資本として国有化することを提案します。
①国有化の必要性:リスクと公共性の再定義
社会的共通資本とは、「人々の生活の質を決定し、社会の持続可能性を担保する重要な資本」であり、市場原理に任せるべきではなく、民主的な手続きを経て管理・運営されるべきものです。
送配電網は以下の理由から、社会的共通資本としての要件を完全に満たしています。
・公共性:電力は生活と経済活動の基盤であり、特定の部門や地域に属するのではなく、全国民が公平に利用できることが求められます。
・非市場性:脱炭素化に向けた巨額の増強・更新投資は、民間企業の採算性や短期的な市場価格に左右されるべきでなく、長期的な国家目標に基づいて実行されるべきです。
・リスクの国民負担化からの脱却:現在、公的融資や公的保証という形で、投資リスクの実質的な国民負担化が始まっています。リスクと費用を国民に背負わせるのではなく、その資産・資本の所有権と管理責任を国が持つべきとする発想です。
②国有化の具体的手法(シン送配電網2050)
国有化は、現状の一般送配電事業者(旧電力大手から分社化した各社)が保有・管理する送配電資産を国が買い取る(買収する)形で行うことが現実的と考えます。
・資産の移管と計上:買収した送配電網は国有資産として明確に資産計上され、電力広域的運営推進機関(広域機関)や新たに設立される公的機関が管理・監督を担う形態を取るものとします。
・運営の分離:インフラの所有と管理(ハード)は国が行い、日常的な運用(ソフト)は、効率性とたゆまない技術革新を追求するため、現行の体制を活かし、民間企業に委託(委託料支払い)するか、または公営化の形態を取ることが考えられます。
この国有化は、シン循環型社会2050のエネルギー自国自給自足の基盤装置であり、災害や国際情勢の変化に強いシン安保2050を支える基礎インフラの一つとして位置づけられます。
2)資産・コスト・財源の考え方(シンMMTの考察と新しい財源モデル)
送配電網を社会的共用資本として運営する上で、最も重要な論点は、その「買収費用、投資費用、運営費用」を、既存の税財源(一般会計)や電気料金(賦課金)に過度に依存せずに賄う「新しい財源モデル」の確立であると考えます。
従来の財源論が財政の制約(税収、国債残高)を前提としていたのに対し、ここでは、「シンMMT(現代貨幣理論)的な発想」に基づいた財源調達の可能性を考察いたします。
① 資産・コスト試算と循環型管理
送配電網の買収・運営に必要な費用は、まず正確に試算される必要があります。これは、以下の「資産買収費」「系統更新・投資費」「運営維持管理費」の三要素から構成されます。
・資産買収費: 民間企業からの送配電資産の時価評価に基づき算出されます。
・系統更新・投資費: 再エネ大量導入、レジリエンス強化のためのデジタル化・強靭化投資に必要な費用です。
・運営維持管理費: 系統運用、保守、人件費など、安定供給を維持するための年間費用です。
これらのコストを賄うための財源は、一般会計に依存するのではなく、システム内での資金循環を基本とする「循環型管理」を目指します。
② 特別財源方式の検討
社会的共用資本である送配電網の費用は、国家の通貨発行権を行使し、日本銀行が「法定通貨の信用」とは切り離した特別な勘定で発行・管理する「限定的な目的の通貨(共用資本専用通貨)」によって賄われる特別会計制度を検討します。
・買収費用: 民間企業からの送配電資産の買収費用は、まず国庫(特別会計)から賄いつつ、将来的に特別財源方式へと移行するロードマップを想定いたします。
・運営・投資費用: 系統運用、老朽化更新、再エネ接続のための新規投資は、**「共用資本専用通貨」**として発行・支給され、国内のインフラ関連事業者への支払いに限定して利用されます。
③ 共用資本専用通貨の設計思想
この特別財源による通貨(共用資本専用通貨)は、その流通と利用に制限を設けることで、インフレ抑制と国内経済の強化を両立させることを目指すものです。
なお、この考え方は、関係サイトhttps://basicpension.jpで、2022年に、日本独自のベーシックインカム、ベーシックペンション構想において提案したものです。
以下を参照ください。
⇒ ベーシック・ペンション法(生活基礎年金法)2022年版法案:2022年ベーシック・ペンション案-1 – 日本独自のBI、ベーシック・ペンション
| 設計要素 | 目的 |
| 用途制限 | 通貨の使途を「送配電網の維持・投資に関連する国内資材、部品調達、および人件費」に限定します。これにより、資金が国内のインフラ供給力強化に集中します。 |
| 利用期限 | 通貨の保有期限を短く設定し、送配電事業者が速やかに国内のサプライヤーに支払うことを促します。これにより、資金の滞留を防ぎ、インフラ投資を加速させます。 |
| 換金と回収 | 事業者が受け入れた通貨は、最終的に日銀が保有資産を原資として法定通貨に換金(または決算時に一定基準で損金処理)できる仕組みを設けることで、通貨の信頼性と流動性を確保します。 |
④ 長期目標:利用基本料の無料化
長期的な目標として、送配電網の維持・運営費用が特別財源方式(共用資本専用通貨)で賄われることにより、利用基本料を無料化することを目指します。
これにより、電気料金に占める送配電コストの負担が軽減され、特に再エネ事業者にとっての系統接続の障壁が大幅に引き下げられることになります。
一般市民生活へも大きく寄与することは明らかです。
最終的に、エネルギーの自由な選択と利用が促進され、国民生活と経済活動の基盤が強化されます。
3)社会的共用資本としての責務と評価
送配電網を社会的共用資本として運営する場合、その責務は「電力の安定供給」に留まらず、広範な「公益の最大化もしくは最適化」へと拡大します。
① 公益の最大化・最適化に向けた責務の再定義
・再生可能エネルギーの無制約な受け入れ: 接続可能量の上限を撤廃し、地域特性に応じた再エネ導入を最優先事項とします。
・レジリエンス(強靭性)の確保: 自然災害やサイバー攻撃に対する強靭性を最重要目標とし、特別財源による投資を集中させます。
・エネルギー・デモクラシーの実現: 地域社会や市民が、系統情報にアクセスし、エネルギーの需給調整に参加できる透明性の高い運営体制を確立します。
② 運営体制の再編とガバナンス
・所有と運営の分離: 資産は国(共用資本)が保有し、系統運用は、国が監督する非営利かつ中立的な専門機関(公社または独立行政法人)に委託します。
・料金体系の抜本的見直し: 共用資本専用通貨による財源方式が確立された後、系統利用料金は、安定供給と環境価値の提供に対する最小限の手数料へと抜本的に見直されるべきであると考えます。
4)シン日本社会2050の資源・エネルギー・環境領域の理念上の要素として
送配電網の国有化と新財源モデルは、単に電力システムの課題解決に留まらず、「シン日本社会2050」が掲げる理念の具体的な要素として組み込まれるべきものです。
シン日本社会2050を構築・構成する5つのシン2050理念体系と、本稿課題の資源・エネルギー・環境領域に属する「送配電網」との関係性について、以下簡単に触れておきます。
・シン循環型社会の象徴であるエネルギー自国自給自足の基盤装置としての送配電網:再エネなどによるエネルギー自給自足循環社会は、強靭で広域的な送配電網があって初めて、その国家目標が達成可能になります。
・シン安保2050を支える基礎インフラとしての送配電網:海外資本や市場原理に左右されない、安定した電力システムは、情報通信や食料生産と同様に、生存権を担保する社会と経済安全保障の生命線です。
・シンMMT2050の適用研究考察対象としての送配電網:公的な必要性に基づく投資を、貨幣発行権を持つ政府が主導するというMMT(現代金融理論)の原則を、送配電網という「自然独占」の公共インフラに限定的に応用し、その有効性を研究することは、新しい財政・金融政策のあり方を探る具体的なテーマともなります。
・シン・イノベーション2050の適用対象としての送配電網:AIやドローンを活用した効率的な運用管理、メンテナンスの高度化などは、国有化された基盤の上で、コストや採算性を気にせず、公共の利益を最優先したシン・イノベーション2050の具体的な運営管理テーマとなるでしょう。またシンMMTを導入することそのものが、シン・イノベーションと評価できます。
5)実現に向けたロードマップ、フェーズの検討
送配電網の社会的共用資本化は、既存の社会経済システムに大きな影響を与えるため、段階的な移行戦略(3つのフェーズ)が必要であると考えます。
次の最終章を兼ねた<まとめ>で、現段階における本稿テーマのの構想化に臨みます。