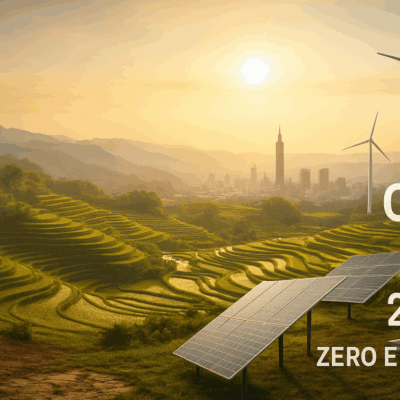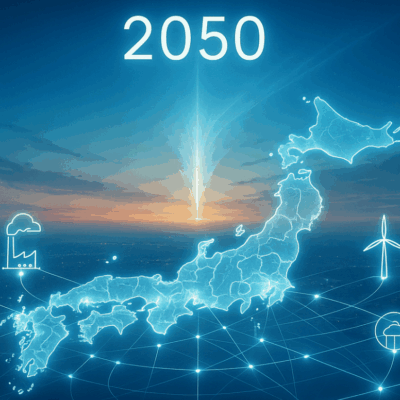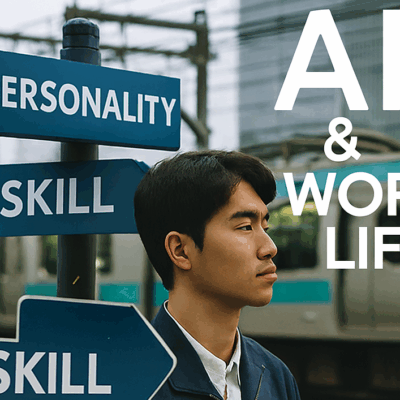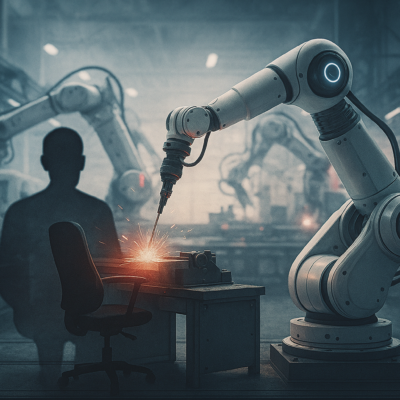社会的共用資本としての送配電網:市場原理を超えた国有化と「シンMMT」新財源モデル
2.送配電網とは?
前章で確認した通り、送配電網はエネルギー・資源戦略の根幹をなすインフラであり、現在、そのあり方が大きな転換期を迎えていると考えるべきです。
ここでは、送配電網の基本的な機能、直面する課題、そして国内の現状等について整理します。
1)送配電網の概要
送配電網とは、発電所で作られた電気を、消費地である工場、オフィス、一般家庭などの需要家に届けるために張り巡らされた物理的なネットワークです。
具体的には、電気を送る「送電線」(高電圧)、配る「配電線」(低電圧)と、それらを接続・変圧する「変電所」などで構成されています。
このインフラは、電力システムにおいて以下の三つの重要な役割を担っています。
① 接続(コネクト):需要家と発電所(大規模電源、再生可能エネルギーなど)を物理的に繋ぐ基盤。
② 輸送(トランスポート):大量の電気を損失を抑えながら、安全かつ安定的に長距離輸送する機能。
③ 周波数・電圧の維持(コントロール):発電と消費のバランスを常時一致させ、電気の「質」(周波数・電圧)を一定に保つための司令塔機能。送電中のロスを減らすために、発電された電気は超高圧変電所で電圧を高められ、複数の変電所を経由して段階的に電圧を下げて届けられます。
送配電網は、水道、ガス、通信などと同様に、「自然独占」の特性を持つ公共性の高いインフラです。
自然独占とは、事業の性質上、特定の地域で複数の企業が競合して設備を整備するよりも、一つの企業が大規模に行う方が、コストが最も低くなり効率的である(規模の経済が極めて大きく働く)状態を指します。
一般的に、同じ地域に複数の送配電網を二重に建設することは非効率的であるため、特定の事業者(日本では地域電力会社の送配電部門)が一元的に運用してきました。
2)送配電網のコストと課題
送配電網は、巨大な社会インフラであるがゆえに、以下のように、維持・更新・増強に関して特有の膨大なコストと、電力自由化後の構造的な課題を抱えています。
①増大する投資コストの内訳
送配電網の整備・維持には、現在、以下の要素により巨額の費用が投じられています。
・設備更新費(老朽化対策):高度経済成長期に集中的に整備された設備の多くが老朽化の時期を迎え、大規模な建て替えや更新が必要。
・送電容量増強(再エネ大量導入):脱炭素目標の達成に向け、再エネ電源を大量に受け入れるための送電線・変電所の大幅な増強。
・災害対策(強靭化):激甚化する台風や地震などによる倒壊・停電を防ぐための、地中化や設備の耐災害性強化。
・デジタル化投資(スマートグリッド化):変動する再エネを効率的・安定的に制御し、電力需給を最適化するためのデジタル技術(スマートメーター、AI制御システムなど)への投資。
② 構造的な課題:電力自由化と投資リスク
かつて、電力会社は「総括原価方式」の下で、投資費用を安定的に電気料金に反映でき、長期の投資回収が保証されていました。
しかし、2016年の電力小売全面自由化後は、この構造が一変しました。
・投資回収の見通しの不安定化:電気料金の決定が市場価格の取引を基準とする構造に転換した結果、長期にわたる大規模投資の回収見通しが不安定になりました。
・投資リスクの集中:その結果、原発や連系線といった巨額かつ十数年を要する長期投資のリスクを、電力会社が単独で負う形になりがちです。
・必要な投資の抑制懸念:リスクに見合うリターンが見込めない場合、採算性の観点から、たとえ社会的に必要であっても、送配電網への必要な投資が十分に行われない懸念が生まれています。これは、前章の日経記事で公的融資の必要性が論じられた背景そのものです。
③ 系統容量不足と安定化の課題
脱炭素化の主役である再生可能エネルギー(特に太陽光や風力)は、立地が偏在し、出力が天候に左右される「変動電源」です。
・系統容量の逼迫:発電所から消費地へ効率的に電気を送るための「送電線」の容量が足りず、再エネの新規導入が抑制される事態(系統制約)が発生しています。
・需給バランス維持の困難化:変動電源の増加に伴い、送配電網の運用者(一般送配電事業者)は、従来の火力主体のシステムよりも、リアルタイムで複雑な需給バランス調整を強いられており、運用コストが増大しています。
④ 地理的な不均衡と連系線リスク
大消費地(都市部)と主要な再エネ適地(地方)が地理的に離れているため、地域間を繋ぐ連系線の増強が不可欠です。
前章で引用した日経記事(北海道―本州の海底送電線)のように、連系線は建設コストが巨額になりやすく、その費用負担や事故・災害時のリスクをどう扱うかが大きな問題となっています。
3)国内の送配電網の状況
国内の送配電網は、2016年の電力小売全面自由化、そして2020年4月以降の**「法的分離(アンバンドリング)」**を経て、制度面では大きな転換を遂げましたが、インフラの維持・更新、そして将来的な需要への対応において、依然として多くの課題を抱えています。
① 制度的な転換(法的分離と広域運用)
・法的分離の進展:地域電力会社(東電、関電など)から、送配電事業部門を切り離し、別会社(東電パワーグリッド、関西電力送配電など)として独立させる分社化(法的分離)は進展しました。
・目的:これは、送配電部門が特定の発電・小売部門に有利な運用をしないように、中立性・公平性を確保するために実施されました。
・一般送配電事業者:現在、国内の送配電網は、北海道から沖縄まで計10社の一般送配電事業者によって運営されています。彼らは、発電・小売の区別なく、すべての事業者に公平に系統への接続機会を提供することが義務付けられています。
・広域運用の改善:電力広域的運営推進機関(広域機関) の設置により、地域間で電力の融通を行うための運用調整は改善し、全国的な需給バランス調整が強化されました。
② インフラの現状と増大する投資需要
送配電網の設備投資は、直近10年で大幅に増加しており、その背景には以下の複合的な要因があります。
・老朽化の進展:高度経済成長期に集中的に整備された送配電設備は、耐用年数を超過、または近づいており、更新投資の需要が巨額に増大しています。
・需要増加への先行投資:AI(人工知能)を活用したデータセンターの増加や、政府が推進するEV(電気自動車)化の進展により、将来の電力需要は増加が見込まれており、これに対応するための先行投資が不可欠です。
・災害対策の強化:台風や地震といった自然災害の激甚化に対応するため、倒壊防止や早期復旧のための設備強靭化投資が求められています。
③ 残された構造的な課題
制度的な進展があった一方で、送配電網を取り巻く環境には、社会的共通資本としての役割を十全に果たす上で、以下の課題が残されています。
・地域間連系線の能力不足:広域運用は進んだものの、主要な再エネ適地と大消費地を結ぶ地域間連系線の能力はまだ不十分です。連系線の増強は巨額のコストと時間を要するため、再エネ導入のボトルネックとなっています。
・真の競争環境整備の課題:法的分離は進んだものの、実態としては旧一般電気事業者が送配電会社の資本の大部分を保有している状態が続いており、真の意味での競争環境整備には課題が残るとの指摘があります。
・特定のエリアにおける財務的ボトルネック:特に東京電力エリアでは、福島原発事故対応に伴う巨額の賠償・廃炉費用という財務負担がボトルネックとなり、送配電設備への迅速かつ大規模な投資実行に影響を及ぼす懸念があります(前章記事2参照)。
・地域間の不均衡:送配電網は国家全体のインフラである一方、老朽化の度合いや再エネのポテンシャル、需要構造などには地域差が大きく、全国的な視点と地域の実情を両立させた均衡ある発展が求められています。
4)送配電網をめぐる最近の動き
送配電網の整備は、単なる電力インフラの維持管理を超え、2050年へ向けた脱炭素化、経済安全保障、産業競争力の維持といった国家戦略の一環として捉えられています。前章で取り上げた金融・資本政策の議論以外にも、送配電網に関しては以下のような重要な動きが見られます。
① 制度と資金調達における構造転換
送配電網への巨額の投資を確実に実行するため、制度と資金調達の面で新たな動きが加速しています。
・レベニューキャップ制度の導入:
2023年度から導入された送配電事業の新たな規制制度です。
これは、事業者が事前に設定した「収入上限(キャップ)」の範囲内で、効率的に投資・事業運営を行うことを促す仕組みです。
従来の「総括原価方式」に比べ、効率化へのインセンティブが高まりますが、大規模な増強投資の資金回収見通しをどう立てるかが課題となっています。
・政策主導の資金投入と資本再編:
長期・巨額のリスクを民間だけで負う限界から、政策主導の資金投入(公的融資の検討)が議論されています(前章記事1)。
また、特に財務負担が重い東電を中心とした外部資本受け入れの議論も進められており、脱炭素投資加速への新たな制度設計と資本戦略が進行中です(前章記事2)。
② インフラの強化と国家戦略化
電力の安定供給と脱炭素の達成に向け、地域を跨ぐ大規模なインフラ整備が国家戦略化しています。
・大規模連系線の整備:
電力広域的運営推進機関(広域機関)主導のもと、北海道ー本州、本州ー九州といった地域間を繋ぐ連系線の増強計画が進行中です。
特に、北海道―本州海底送電線や九州から本州への増強計画など、広域連系強化が不可欠であり、これには公的保証を付けて民間融資を誘う動きが見られ、公的支援の議論(記事1、参考記事)と密接に関連しています。
・地域間電力格差への対応:
再エネ導入適地である地域と大消費地である都市部との間で、電力系統の容量や投資状況に電力格差拡大の懸念が生じており、広域連系線の整備はこれに対応する目的も持っています。
・需要増対応の投資拡大:
AI(人工知能)を活用したデータセンターや半導体工場の国内新設に対応するため、電力会社は送配電網の増強に力を入れており、これを受けて関連設備メーカーも増産を急いでいます。
・災害対策の強化:阪神大震災の経験を踏まえるなど、激甚化する災害に備え、災害に強い送配電網の構築に力が入れられています。
③ 技術革新と系統利用ルールの見直し
既存の系統を最大限に活用し、将来の電力システムに対応するため、運用ルールと技術の進化が同時並行で進んでいます。
・系統利用ルールの見直し:再エネの大量導入を円滑にするため、「ノンファーム型接続」や「日本版コネクト&マネージ」といった、系統を柔軟かつ効率的に利用するための運用ルール(制約付き接続や出力制御の強化)が導入・拡大されています。
・AIによる効率化と信頼性向上:AI技術を活用して送配電事業者の業務効率化、設備の信頼性向上、さらには顧客体験の向上が図られています。
・送電線の多用途活用:電力会社やJR東日本は、送配電網をドローンの航路として実用化する計画を進めており、送電線の点検だけでなく、緊急時の物流などへの応用が期待されています。
これらの動きはすべて、2050年へ向けて送配電網の整備を急ぐ必要性と、従来の「自然独占・地域独占」モデルでは対応しきれない構造的な課題が存在していることを示しています。
次の章「3.社会的共通資本・社会的共用資本としての送配電網のあり方」では、この特殊な社会インフラを、経済学者・宇沢弘文が提唱した社会的共通資本という視点から論じることになります。
なお、宇沢氏による「社会的共通資本」の理念・概念を反映させた「シン社会的共通資本2050」。
その共通概念として、その資本もしくは資産のユーティリティ(共用性)に重点を置き、「社会的共用資本」という呼称を、そこでは展開しました。
以後の本稿ではその「社会的共用資本」という用語を使います。