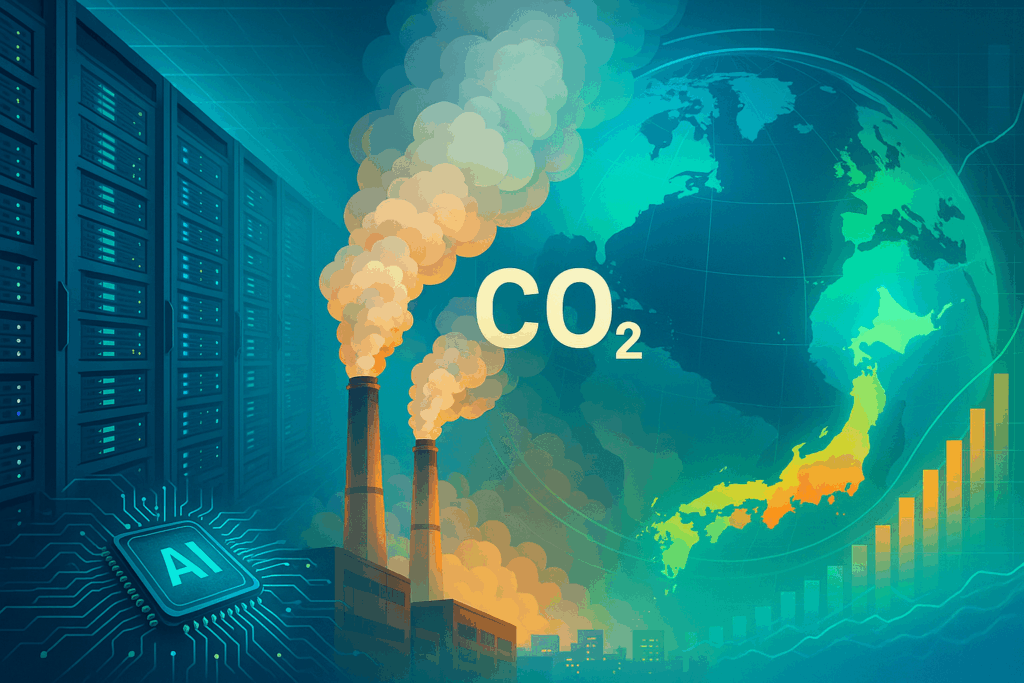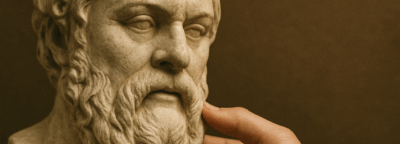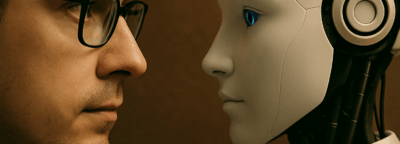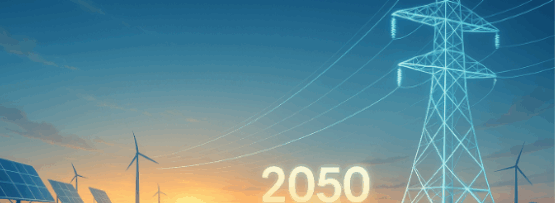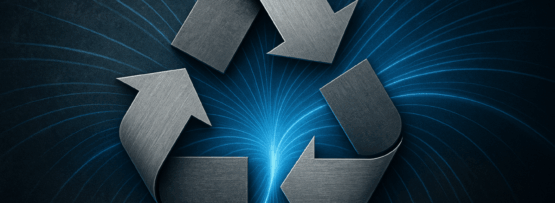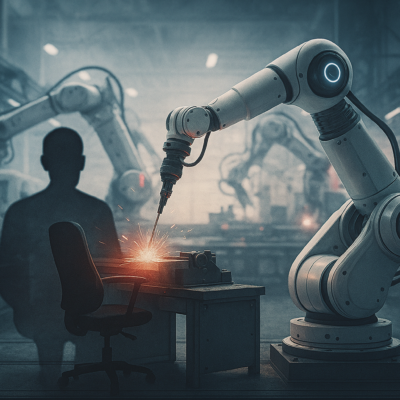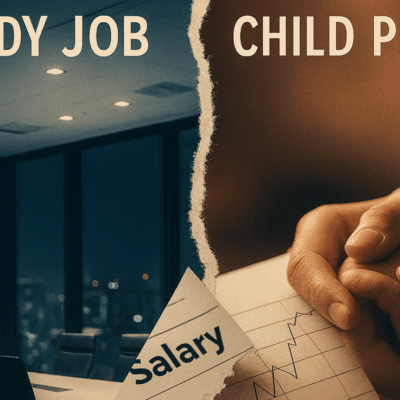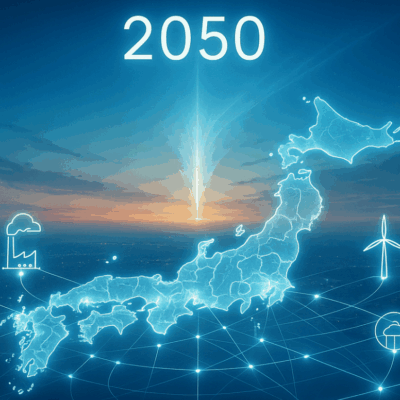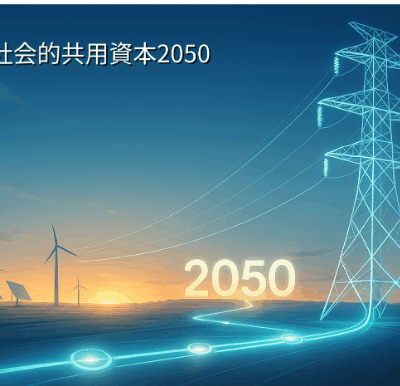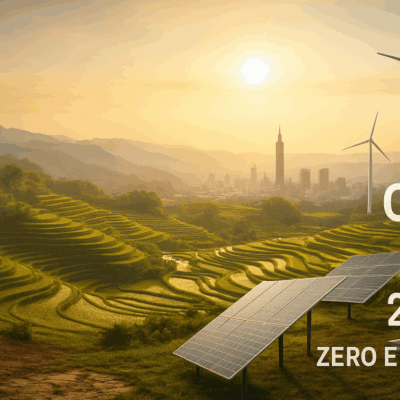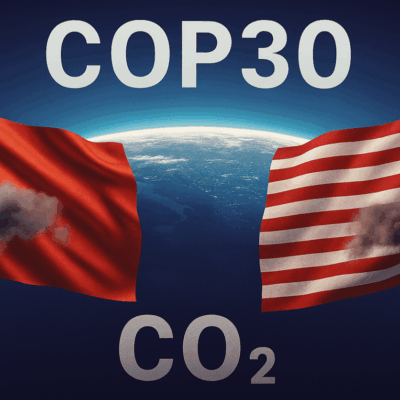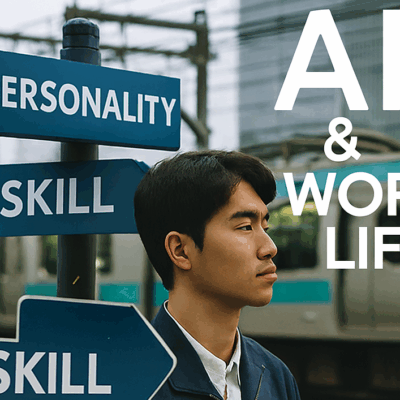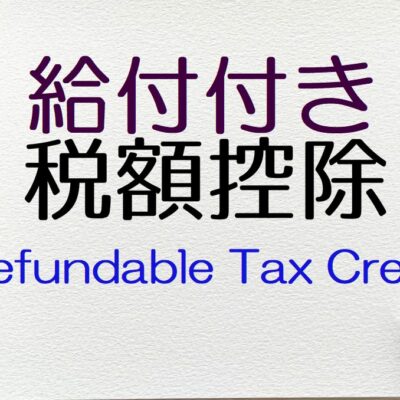2. CO₂排出の現状:エネルギー需要爆増にどう対応するか
地球温暖化の進行を抑えるためには、温室効果ガス、特に二酸化炭素(CO₂)の排出実態を正確に把握することが不可欠です。
本章では、国別・産業別・エネルギー源別の現状を確認した上で、AI・半導体時代に急増するエネルギー需要の新たな課題、
そして国際的な合意と目標・予測とのギャップを考察します。
1) 世界と日本のCO₂排出実態
① 国別(主要排出国の比較)
世界のCO₂排出量は2023年時点で約370億トンに達し、依然として上昇傾向にあります。
国別では以下の通りです(IEA・世界銀行データ参照)。
| 国・地域 | 排出量(2023年) | 世界シェア | 備考 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 約108億トン | 約29% | 世界最大の排出国。石炭依存率が高いが、再エネ投資も急増。 |
| 米国 | 約47億トン | 約13% | シェールガス利用拡大で石炭依存減。再エネ比率は上昇中。 |
| インド | 約28億トン | 約8% | 経済成長に伴い増加傾向。石炭火力が主力。 |
| EU諸国 | 約25億トン | 約7% | 1990年比で約30%削減。脱炭素政策の先進地域。 |
| 日本 | 約10.4億トン | 約3% | 排出第5位。エネルギー輸入依存が高く、再エネ導入拡大が課題。 |
日本は総排出量こそ減少傾向にあるものの、一人当たり排出量では依然としてOECD諸国の中でも上位に位置します。
エネルギー構成の転換と産業部門の効率化が急務です。
② 産業別の排出構造
産業別では、エネルギー転換部門(発電・熱供給)が全体の約40%を占め、
続いて製造業(約25%)、運輸(約15%)、**家庭・業務部門(約10%)**が続きます。
・発電:火力発電(特に石炭・LNG)の比率が依然高く、排出量の最大要因。
・製造業:鉄鋼・セメント・化学産業など高温プロセスを必要とする業種で排出が集中。
・運輸:自動車・航空・船舶による化石燃料消費が主要因。
・家庭:暖房・給湯・電化製品のエネルギー消費が影響。
この構造は日本でもほぼ同様で、特に製造業・運輸業での排出削減が課題となっています。
③ エネルギー源別の詳細状況
世界全体で見ると、2023年時点の一次エネルギー供給の内訳は以下の通りです。
・石炭:27%
・石油:31%
・天然ガス:23%
・再生可能エネルギー(水力・太陽光・風力など):16%
・原子力:3%
つまり、依然として約8割が化石燃料に依存しているのが現実です。
日本も同様で、2010年の原発事故以降、化石燃料依存率が一時90%を超え、近年でも70%台を維持しています。
再エネ導入の伸び悩みと送電インフラ制約が課題であり、「再エネ+蓄電+分散電源」の仕組みづくりが求められています。
2) AI社会・半導体製造増大に伴うエネルギー需要の爆発
AI技術の急速な普及と、半導体製造能力の増大は、新たなCO₂排出源を生み出しています。
AIの学習や推論を支えるデータセンターは、膨大な電力と冷却エネルギーを必要とします。
現在、世界のデータセンターが消費する電力は世界総電力消費の約3〜4%に達し、
2030年には約10%に拡大するとの試算もあります(IEA, 2024)。
特に生成AI(ChatGPTなど)の処理は高演算負荷を伴うため、電力消費量は従来の数倍規模に増加しています。
また、AI開発を支える半導体製造も高エネルギー産業の一つで、製造過程で多量の電力と水資源を消費します。
たとえば、台湾のTSMC(世界最大の半導体製造企業)は、
単一工場で年間最大70億kWh以上の電力を使用するとされ、これは中規模都市1年分の消費量に相当します。
これらの事実は、「デジタル化=脱炭素」とは限らないことを示しています。
AI社会化は効率化・自動化を進める一方で、電力需要とCO₂排出を押し上げる「デジタル・パラドックス」を抱えており、
エネルギー源の再生可能化が進まなければ、温暖化の抑制どころか逆行するリスクもあるのです。
3) 国際枠組みと目標・予測
地球温暖化対策は、国際社会が協調して取り組むべき課題として1990年代以降一貫して議論されてきました。
その流れをたどると、京都議定書 → パリ協定 → COP30(次期交渉)という3つの節目に整理できます。
① 起点としての京都議定書(1997)
1997年に採択された京都議定書は、初めて先進国に法的拘束力を伴う温室効果ガス削減目標を課した国際的枠組みです。
日本は議長国として重要な役割を果たし、2008〜2012年の第1約束期間で1990年比6%削減を約束しました。
しかし、当時の枠組みは先進国のみを対象とし、中国やインドなど新興国を含まなかったため、
結果的に世界全体の排出削減には十分に機能しませんでした。
② 合意の再構築:パリ協定(2015)
2015年のパリ協定は、京都議定書の反省を踏まえ、すべての国が参加する枠組みとして成立しました。
法的拘束力は限定的ながら、「自主的削減目標(NDC)」を各国が提出し、5年ごとに進捗を見直す仕組みを導入しています。
また、「世界の平均気温上昇を産業革命前比で1.5〜2.0℃未満に抑える」ことを共通目標として掲げました。
この「1.5℃目標」は、将来の気候リスクを最小化するための臨界値とされています。
③ 最新交渉の焦点:COP30(2025年11月開催)
2025年11月10日〜21日、ブラジル・ベレンにて第30回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP30)が開催されています。
この会議は、パリ協定以降の進捗を評価し、2030年・2050年目標への中間調整を行う重要な会議。
パリ協定で掲げられた「産業革命前比1.5℃」目標を達成すべく、各国の自主的削減目標(NDC: Nationally Determined Contributions)更新、気候資金の動員、適応・損失・被害対応が主要議題となりました。
だが、トランプ米国は、パリ協定からの離脱を既に発表済み。
対極的に中国の突出した積極的な取り組みの動きはあるもののスタンドプレイの誹りを免れえません。
(参考)
⇒ MAGA vs MCGHH:温暖化対策を「無視」する米国と「主役」を狙う中国【COP30と日本の課題】 – ONOLOGUE2050
現時点では、みずから提出されたNDCや政策行動を踏まえても、2100年までに気温上昇が約2.7℃に達する可能性がある(UNEP, 2024)とされています。
また、米国の政策不安定化、中国・インドの排出増加、ロシア・中東の資源依存構造が、「国際合意の実効性」を弱めています。
それにより、「目標(1.5℃)と実態(2.7℃)」の間に、約1.2℃分の実態と目標とのギャップが改めて浮き彫りになっています。
このギャップを埋める鍵は、再生可能エネルギーとCCUSの導入拡大、そして制度的アプローチ(カーボンプライシング・排出権取引)の実効化にあります。
CO₂排出の現状は、国際社会の努力にもかかわらず依然として高止まりしています。
AI社会化・半導体需要の拡大など、新たなエネルギー消費構造が重なり、
「経済成長」と「脱炭素」の両立が難しい局面に入っています。
次章では、こうした背景を踏まえ、CO₂削減を実現するための具体的な技術・制度的手法を詳しく見ていきます。