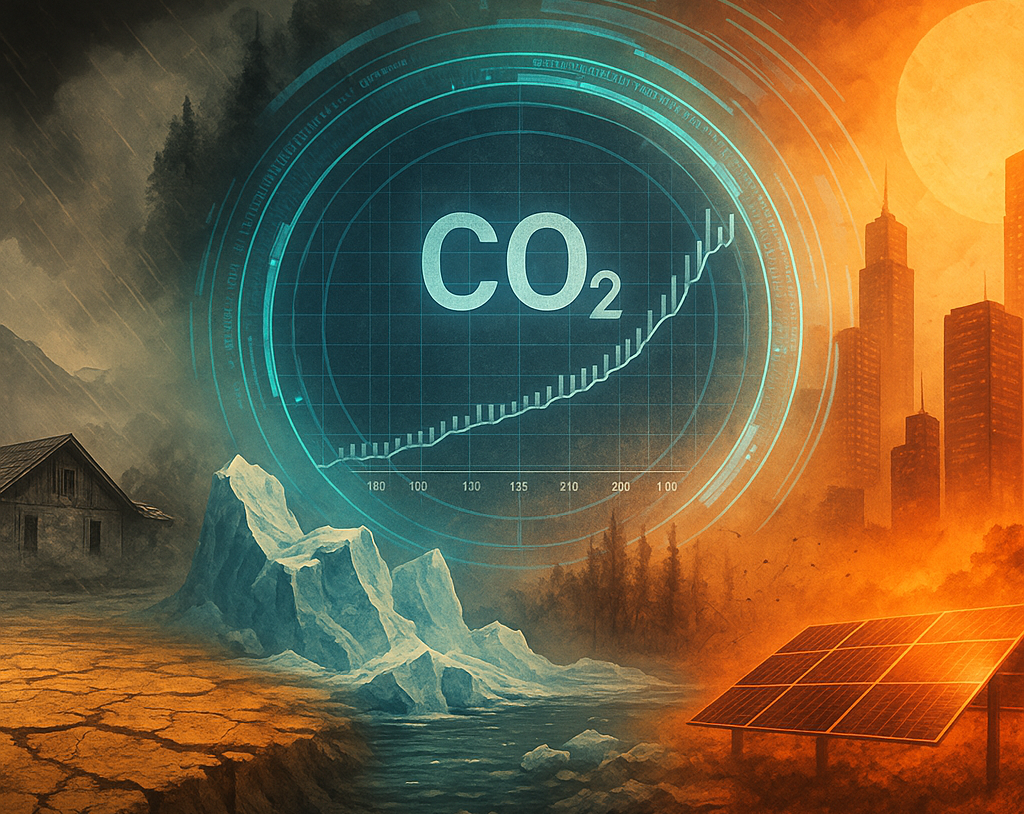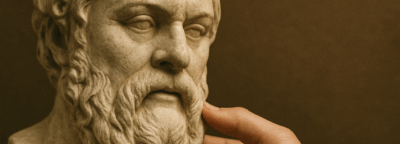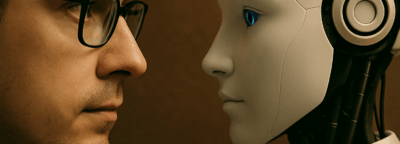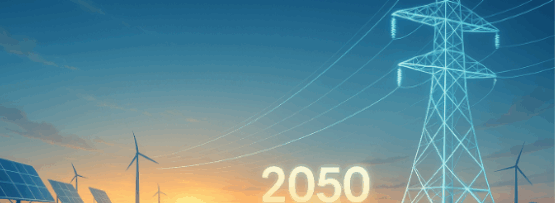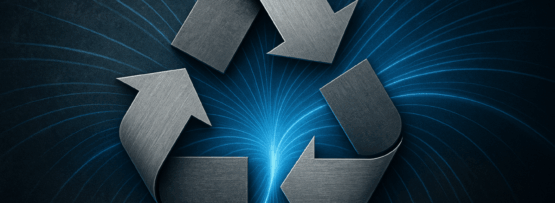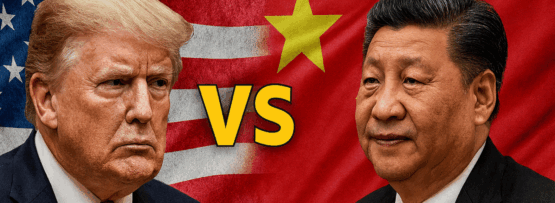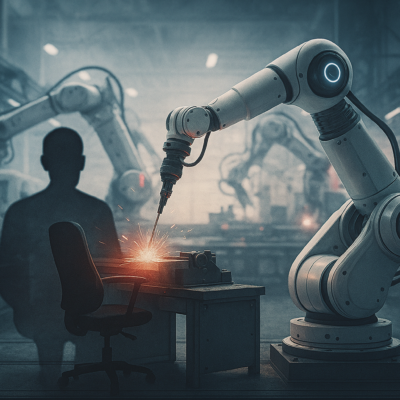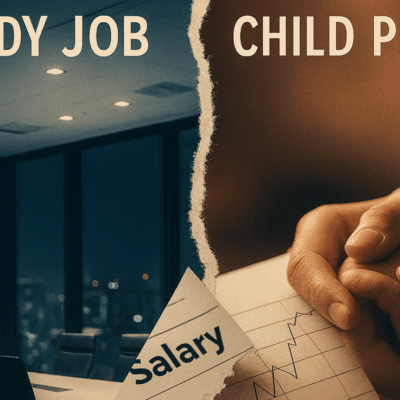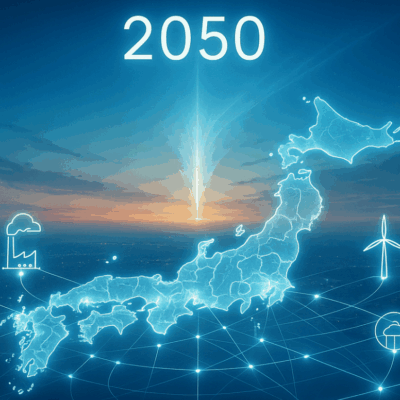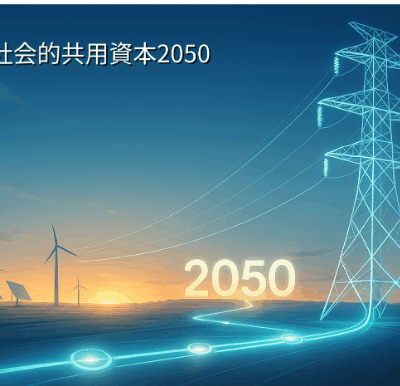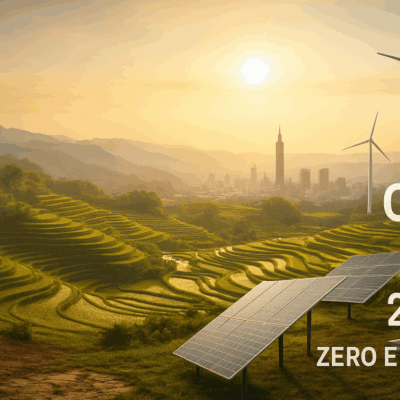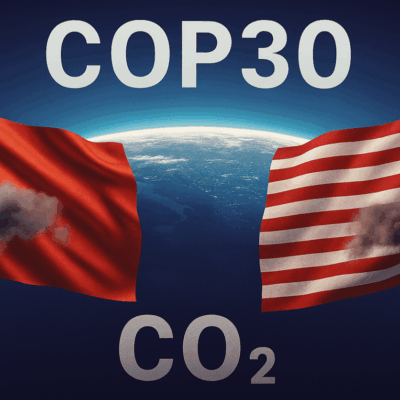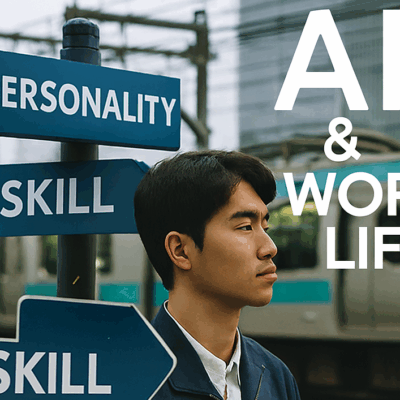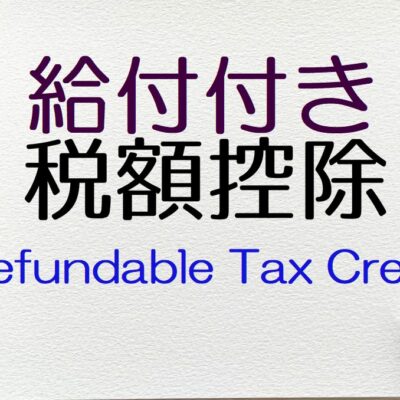CCUS(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage)はCO2削減、温暖化対策の切り札になるか
はじめに
先月2025年10月8日付の日経に以下の記事が掲載されました。
⇒ 三菱ガス化学、万博由来のCO2を新潟で貯留へ 地元に情報求める声 – 日本経済新聞
この記事で強く惹かれたのが、「CO2の貯留」「埋め立て」という手法と技術です。
丁度、前回、COP30における温暖化対策における米中の対応の違いを取り上げて、以下を本サイトに投稿しました。
⇒ MAGA vs MCGHH:温暖化対策を「無視」する米国と「主役」を狙う中国【COP30と日本の課題】 – ONOLOGUE2050
CO2の貯留は、温暖化対策とも繋がるもの。
その認識から、本稿を企画し、その構成を設定して考察し、本稿に取り組みました。
1. 地球温暖化の危機の構造とリスク|関連基礎用語も確認
地球温暖化は、すでに世界各地で私たちの生活を脅かす現実の危機となっています。
猛暑、豪雨、洪水、異常気象──これらは単なる自然現象ではなく、地球の気候システムが大きく揺らぎ始めている兆候です。
本章では、温暖化の基本的な仕組みと、その影響が社会・経済・生活にどのようなリスクとして現れているのかを整理し、併せて関連する基礎用語を確認していきます。
1) 地球温暖化の基本メカニズム
地球温暖化とは、大気中に蓄積された温室効果ガス(GHG:Greenhouse Gases)によって地表付近の平均気温が上昇する現象を指します。
主な温室効果ガスは、二酸化炭素(CO₂)、メタン(CH₄)、亜酸化窒素(N₂O)、フロン類などです。
地球は太陽からのエネルギーを受け取り、その一部を宇宙へ放出してエネルギーの均衡を保っています。
しかし、温室効果ガスが増えるとこの放射エネルギーが大気に閉じ込められ、地表付近の熱が逃げにくくなるのです。
これが「温室効果」と呼ばれ、産業革命以降の化石燃料利用拡大によってそのバランスが急速に崩れつつあります。
IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の報告によると、産業革命前と比べて地球の平均気温はすでに約1.1℃上昇しています。
この上昇幅が1.5℃を超えると、極端な気象現象や海面上昇、生態系への不可逆的な影響が現れるとされています。
2) 地球温暖化・気温上昇がもたらす社会・経済・安全保障リスク
地球温暖化は、単に気温が上昇するという現象にとどまりません。
気候システム全体のバランスを変え、異常気象の頻発化・自然災害の激甚化・生態系と経済活動の崩壊リスクを同時に引き起こしています。
ここでは、私たちの生活や社会基盤にどのようなリスクが及ぶのかを、5つの視点から整理してみましょう。
① 異常気象の増加と自然災害の激甚化
近年、地球温暖化の影響として最も実感しやすいのが「異常気象」の増加です。
日本を含む世界各地で、猛暑・豪雨・大型台風・干ばつ・森林火災・豪雪などの極端現象が常態化しています。
気温上昇によって大気中の水蒸気量が増加し、積乱雲の発達が促進されるため、**短時間に局地的豪雨(線状降水帯)**が発生しやすくなっています。
また、海面温度の上昇は台風の勢力を強め、より大規模な風水害をもたらしています。
・2023年には、世界平均気温が観測史上最高を記録し、日本では、今年2025年には、過去にない記録的猛暑日が続出しました。
・欧州では熱波による干ばつ・山火事が頻発し、カナダやギリシャでは大規模な森林火災が長期化しました。
こうした現象は、気候変動が「異常」ではなく「常態化」しつつあることを示しています。
日本でも、洪水・土砂災害・暴風被害などの発生頻度と被害規模が明らかに増加しており、住民生活と地域経済の両方に深刻な影響を及ぼしています。
② 健康への影響
地球温暖化は、人間の健康と生命に直接的な影響を与えます。
夏季の平均気温上昇により、熱中症による救急搬送者数や死亡者数が年々増加しています。
また、ヒートアイランド現象の影響で都市部の夜間気温が下がらず、睡眠障害や慢性的な疲労の増加といった形で生活の質を低下させています。
さらに、気候変化は感染症の分布にも影響します。
蚊を媒介とするデング熱やジカ熱など、熱帯性感染症の北上・定着リスクが高まっており、WHOも警鐘を鳴らしています。
加えて、アレルギー疾患や花粉飛散の長期化など、呼吸器疾患への負担も増加しています。
③ 食料生産・農業への影響
気温上昇と降雨パターンの変化は、農作物の生育環境に大きな影響を及ぼしています。
特に日本では、米の品質低下(高温障害による白未熟米の増加)や果樹の開花時期の変化など、農業経営への打撃が広がっています。
世界的にも、干ばつや洪水による穀物収量の変動が顕著で、食料価格の高騰を招く要因となっています。
また、漁業分野では海水温の上昇による漁場の北上・魚種構成の変化が進行しており、国内外の食料供給構造を揺るがす事態となっています。
このように、地球温暖化は「農業」「漁業」「食料供給」の全体にわたって影響を及ぼし、食の安全保障リスクとしても顕在化しています。
④ サプライチェーンと経済活動への影響
自然災害や気候リスクの増大は、グローバル経済におけるサプライチェーンの脆弱性を浮き彫りにしています。
一つの台風や洪水が、世界中の生産・物流に波及する時代です。
・2011年の東日本大震災では、半導体部品の供給停止が世界中の自動車産業に影響を与えました。
・近年では、東南アジアの洪水や米国の干ばつが、製造・食品・エネルギー価格の変動を引き起こしています。
企業にとっては、気候リスクを財務リスクとして管理すること(TCFD対応)が新たな経営課題となりつつあります。
さらに、保険業界や金融業界も自然災害リスクを織り込むようになり、気候変動が経済全体の構造的変化を誘発しています。
⑤ 社会的・安全保障リスク
温暖化の影響は、国家間・地域間の安定にも直結します。
水資源の枯渇、農地の減少、食料不足などによって、**移民や「気候難民」**が増加する恐れがあります。
また、海面上昇により島嶼国や沿岸都市が居住不能になるケースも想定されています。
これらは、国境を越えた人道危機・地政学リスクを引き起こす可能性があり、
「気候安全保障(Climate Security)」という新たな政策領域として各国政府・国連が取り組みを強化しています。
地球温暖化によるリスクは、健康・食料・経済・安全保障といった個別分野にとどまらず、
社会全体の機能を連鎖的に揺るがす構造的危機へと拡大しています。
特に近年では、「異常気象と自然災害」が人々の生活に最も直接的な影響を与える形で進行しており、
それが同時に企業・政府・地域社会のレジリエンス(回復力)を問う時代に入っています。
この現実を踏まえ、次章では、CO₂排出の現状とその削減の方向性を具体的に見ていきます。
3) 基礎用語の整理と相互関係
地球温暖化対策を理解するためには、頻繁に用いられる関連用語の正確な意味と相互関係を整理しておくことが重要です。
ここでは、本稿で登場する5つの主要用語を確認します。
温暖化対策に関連する基本的なキーワードの「違い」と「つながり」を整理し、次章以降の政策・技術理解の前提を整えることを目的としています。
① 脱炭素(Decarbonization)
「脱炭素」とは、社会全体からCO₂などの炭素由来の温室効果ガスの排出を極力減らす取り組みを指します。
産業・交通・エネルギー・建築・農業など、あらゆる経済活動の仕組みを低炭素化する包括的な概念であり、「2050年カーボンニュートラル実現」の具体的行動目標の根幹をなす考え方です。
② CO₂ゼロ(Zero Emission)
「CO₂ゼロ」とは、特定の活動・製品・サービスにおいてCO₂の排出を実質的にゼロにすることを意味します。
ただし、現実には排出ゼロ=排出が全くない状態ではなく、排出量をできるだけ減らし、残りを森林吸収やカーボンクレジットなどで相殺(オフセット)する形が多く採用されています。
この「実質ゼロ」が後述するカーボンニュートラルの基本概念です。
③ カーボンニュートラル(Carbon Neutral)
「カーボンニュートラル」とは、排出されるCO₂量と吸収・除去されるCO₂量が均衡する状態を指します。
つまり、「排出=吸収+除去」となることで大気中のCO₂濃度を増やさない状態です。
日本政府も2050年までにこの状態の達成を目標としています。
この達成には、再生可能エネルギー、CCUS、カーボンクレジットなど、さまざまな手段が組み合わされます。
④ カーボンプライシング(Carbon Pricing)
「カーボンプライシング」とは、CO₂排出に経済的な価格を付与する仕組みです。
排出にコストを課すことで、企業や個人に排出削減のインセンティブを与える政策的手法で、代表的な制度として「炭素税」や「排出権取引制度(ETS)」があります。
「環境負荷をコスト化する」という考え方は、環境経済学的アプローチとして、近年急速に国際標準となっています。
⑤ カーボンクレジット(Carbon Credit)
「カーボンクレジット」とは、排出削減や吸収活動によって生じた削減量(または吸収量)を取引可能な“証書化”したものです。
企業や国が自らの排出を相殺(オフセット)するために購入することができ、国内外で市場が拡大しています。
森林保全プロジェクトや再エネ開発、メタン削減事業などが主な発行源となっています。
カーボンプライシングが「排出コストの可視化」であるのに対し、
カーボンクレジットは「削減・吸収努力の市場化」と言えます。
両者を適切に組み合わせることで、環境政策の実効性を高めることができます。
本章では、地球温暖化の仕組みとそのリスク構造、そして関連する基本用語の整理を行いました。
温暖化の問題は「科学的課題」であると同時に、「経済・社会・生活安全保障上の構造的リスク」であることが明らかです。
次章では、この背景を踏まえて、CO₂排出の現状と予測、そして削減目標の具体的な方向性を見ていきます。