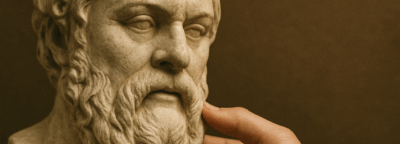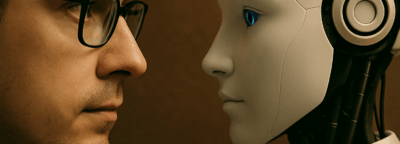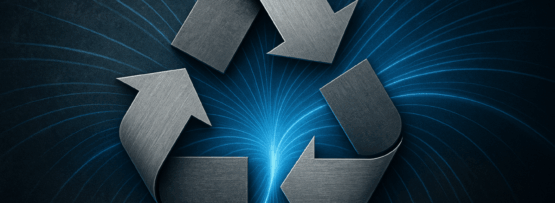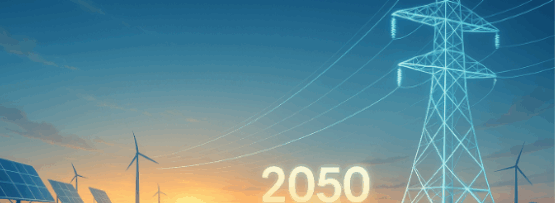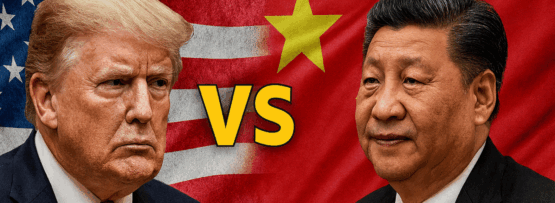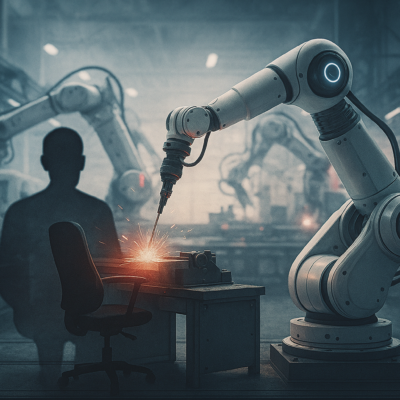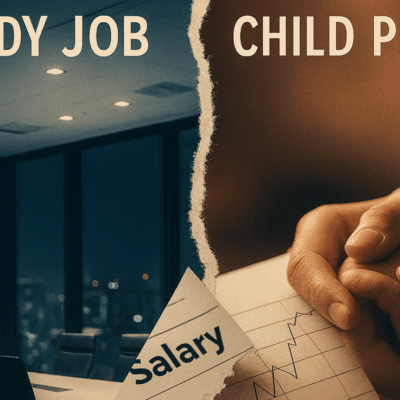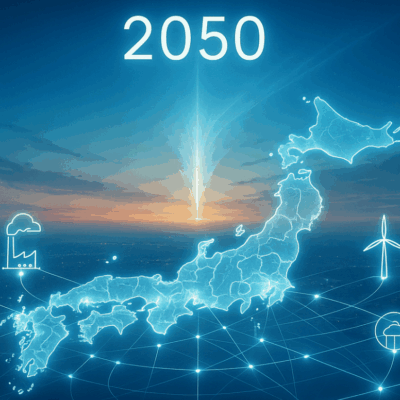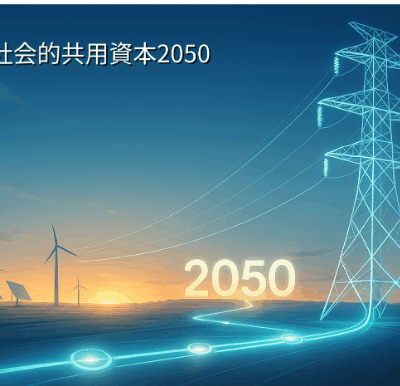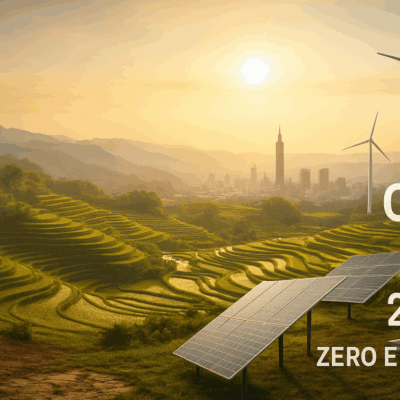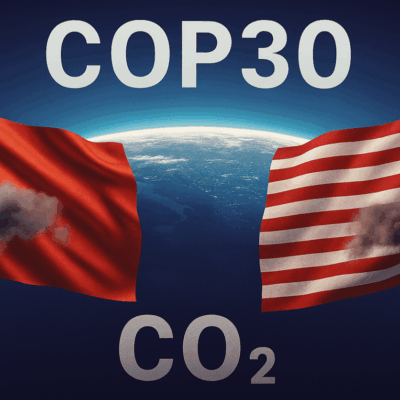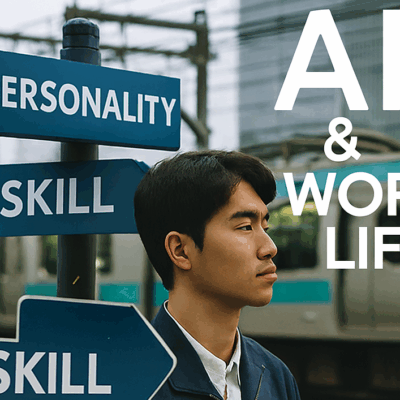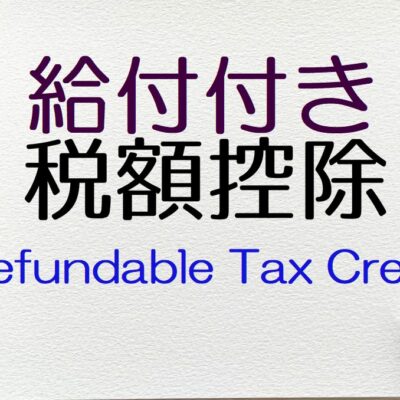2.理念先行の欧州、EU諸国の環境問題・地球温暖化対策への引け腰
それでは、本来主役の一つあるべき、欧州・EUの動向について、触れておこう。
気候変動対策の理念的旗手と見られてきた欧州連合(EU)の主要国は、中国や米国とは対照的な動向を示している。
英国及びEU主要国のCO2排出実績
最新の推計(2024年推計または直近のデータに基づく)によると、EU域内の排出量は長期的な削減傾向にある。
その主要国の排出量は以下の通りである。(対日本比較含む)
| 国名 | 年間排出量(百万トン) | 順位(世界の目安) | 特徴 |
| 日本 | 約988.8 | 5位 | 比較対象としてのG7国 |
| ドイツ | 約620 | 7~8位程度 | EU最大の排出国、工業の重鎮 |
| 英国 | 約320 | 15位前後 | EU離脱国、急速な排出削減を達成 |
| イタリア | 約310 | 16位前後 | G7主要国の一つ |
| フランス | 約290 | 18位前後 | 原子力比率が高く排出量が少ない |
※注: 欧州主要国の具体的な順位は、イラン、韓国、インドネシア等新興国が接近・追い越しつつあるため、年によって変動する。
排出量とEUの立ち位置
上記のデータから読み取れるのは、EU主要国は、中国・米国・インド・ロシアといった巨大排出国に比べ、排出量の規模がはるかに小さいという事実である。
・EU最大の排出国であるドイツ(約6.2億トン)でさえ、世界5位の日本(約9.89億トン)を下回る。
・EU主要3カ国(ドイツ、フランス、イタリア)の合計排出量を合わせても、中国(約119.0億トン)の1割程度に過ぎない。
これは、EUが長年にわたり排出量取引制度(EU-ETS)やFit for 55パッケージといった強力な政策を実行し、排出量を1990年比で大幅に削減してきた成果といえる。
彼らは「経済成長と排出量削減は両立できる」という国際的なレガシー(遺産)を築いてきた。
しかし、それは、どちらも比較的規模が小さい段階だった故可能だったと言っても良いかと思う。
「理念先行」から「実利優先」への転落とリーダーシップの喪失
しかし、EUが主導する温暖化対策には、現在大きな影が差している。
・理念先行:
EUは排出量削減の面で世界をリードしてきた。
しかし一方、その厳しい規制(国境炭素調整メカニズム/CBAMなど)は域内産業の競争力低下を招き、「脱炭素化」と「産業競争力強化」の両立が難しくなっている。
・引け腰の背景:
エネルギー価格の高騰や、ロシア・ウクライナ戦争後のエネルギー安全保障問題、そして中国の再生可能エネルギー分野での圧倒的な台頭により、EUは実利を優先せざるを得ない状況に直面している。
反移民や反EUの勢いが増している内政の不安要因も間接的には影響していると言えよう。
・決定的な示唆:
かつて温暖化対策の「灯台」であったEU諸国は、経済的な重圧と内政の不安定化により、その国際的なリーダーシップを決定的に喪失しつつある。
彼らの「引け腰」こそが、国際社会における温暖化対策のヘゲモニーを、トランプ不在に乗じた習近平中国(MCGHH)へと、さらに傾斜を強くする最大の要因となっていると言えるだろう。
COP30をめぐる日経報道からの要約
欧州からはスターマー英首相、フランスのマクロン大統領、ドイツのメルツ首相とCOP30に主要国の首脳は揃った。
しかし、域内は政治が安定せず、環境対策への意欲は落ちている。
欧州連合(EU)では40年までに1990年比で温暖化ガスを90%削減する新たな目標を決めた。
一部の削減分は外国の炭素クレジット購入でまかなうことを認め、当初案から後退している。
これらの妥協は、EUがもはや理念のみでは世界を牽引できないという現実を象徴しており、そのリーダーシップの空洞化とそこからの逃避を裏付けるものに他ならない。