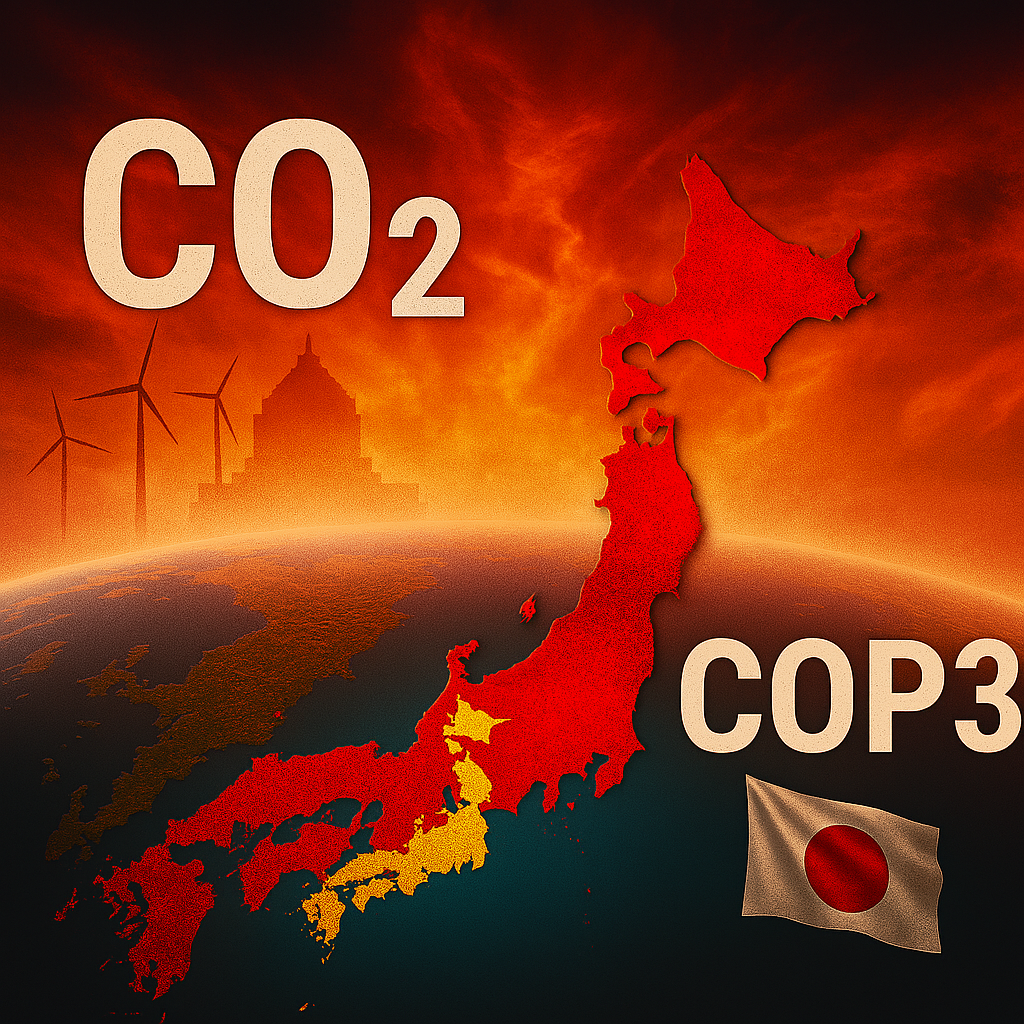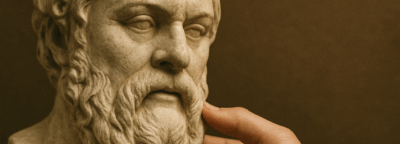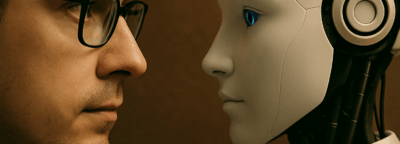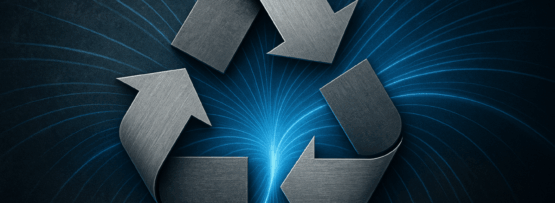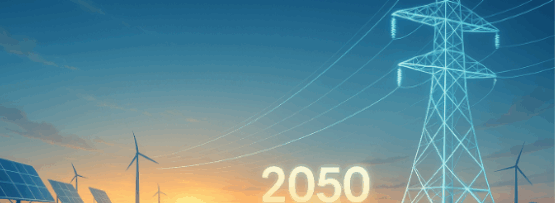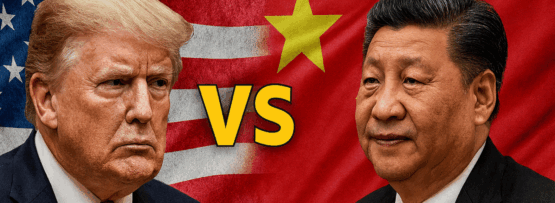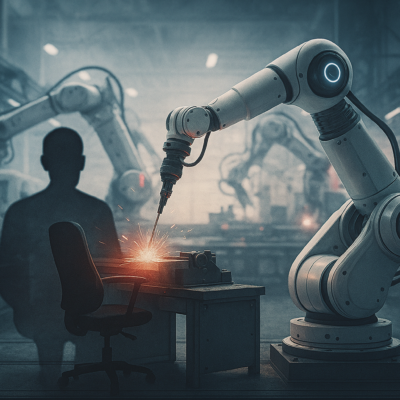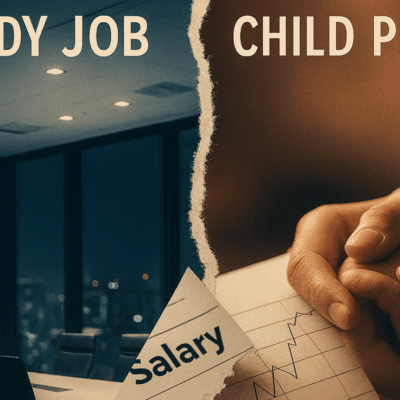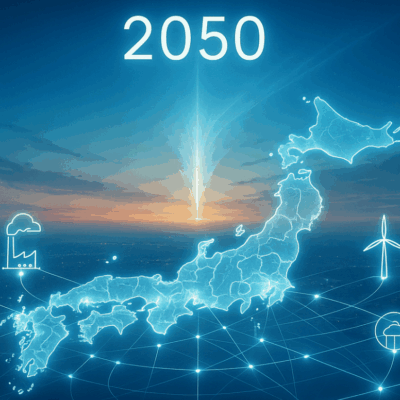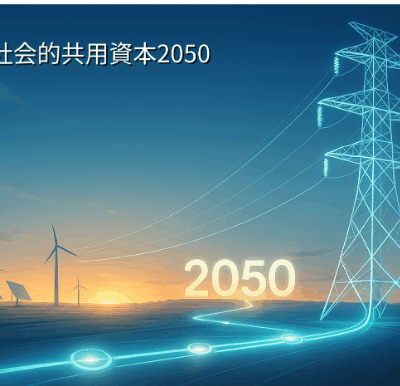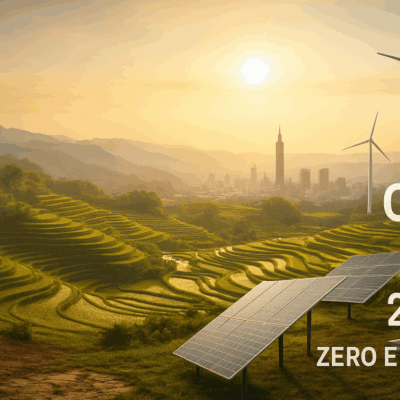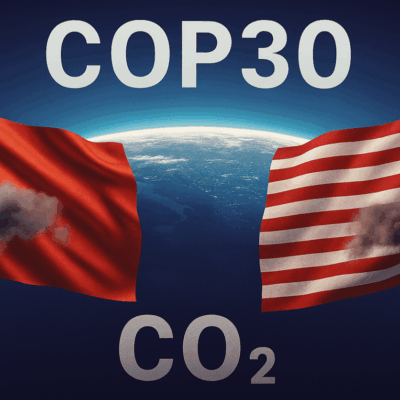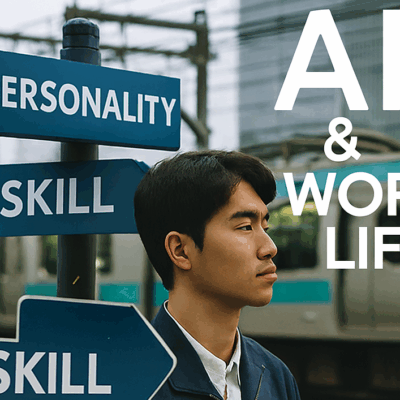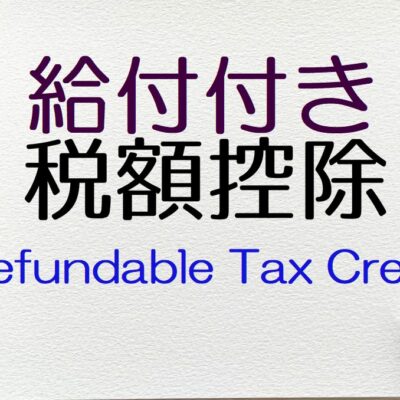3.高市新政権下における温暖化対策と日本の課題
日本のCO2排出量とランク
日本は、世界のCO2排出量ランキングで第5位(9.74億トン、世界の約2.9%)という位置にある。
中国・米国・インド・ロシアに続く大排出国であり、先進国として温暖化対策への貢献が国際的に強く求められていると言えよう。
排出量は全体で見れば上位だが、近年は着実に削減傾向にあることも事実である。
しかし、この第5位という順位は、気候変動対策への国際的な議論において、日本が決して傍観者ではいられないことを示しているのである。
COP30に向けての日本の政策
就任来、積極的に外交を展開し、高い内閣支持率を得ることに成功した感がある高市シン政権。
しかし、国会対応を優先して、今回のCOP30への参加は見送った。
10月の所信表明演説では「地域の理解や環境への配慮を前提に、脱炭素電源を最大限活用する」と明らかに。
日本政府は2月に2035年度時点で13年度比60%、40年度時点で73%の削減目標を定めている。
日本の温暖化政策のあるべき形と課題
世界第5位の排出国である日本は、国際的な責任と同時に、経済安全保障、産業競争力、そして国土の安全という複数の難題を抱えながら温暖化対策を進めるべきだろう。
高市新政権が目指すべき温暖化政策の「あるべき形」は、「持続的な国力維持」と「国際社会への責任遂行」のバランスをいかに取るか、という点に集約することができるだろうか。
以下具体的な政策を整理してみた。
1)「脱炭素電源最大限活用」の具体化と課題
高市総理が所信表明で掲げた「脱炭素電源を最大限活用する」という方針は、原子力の活用を明確に視野に入れたものだ。
・課題:
2035年度時点で13年度比60%削減という野心的な目標を達成するためには、再生可能エネルギーの導入拡大に加え、安全性の確保と地元の理解を大前提とした原子力発電所の再稼働・リプレースが不可欠となる。
中長期的には、新しい小型原子炉の構想と具体化も選択肢とすべきではないかと、最近は考えている。
その為の国民的理解・合意と必要な「地域の理解」を得るプロセスが、政治的、社会的な障壁となることは言うまでもない。
現実的かつ説得力をもったリーダーシップが問われるところである。
・あるべき形:
エネルギーミックスにおける原子力の位置づけを曖昧にせず、安全性と安定供給、そして原子力発電が最も優位性を持つ排出削減を両立させる明確なロードマップとその根拠を示すべきであろう。
2)国際的な「支援国」としての役割の再定義
仮説としてのMCGHHの文脈で、中国が温暖化対策を「ヘゲモニー獲得の手段」の一つとして利用する中、米国が不在となるCOPの場で、日本は先進国の一国家として、グローバル社会における「立ち位置」を再検討・再定義する必要がある。
CO2排出において5番目に多い国としても。
・課題:
G7の一員として、途上国への資金・技術支援は不可欠だが、国内の財政状況との兼ね合いを考慮しつつ、中国が推し進める途上国支援(グリーン・シルクロード構想など)への対抗軸を示す必要がある。
・あるべき形:
日本が強みを持つCCUS(CO2回収・利用・貯留)や水素・アンモニアといった革新技術をパッケージ化。
アジア・太平洋諸国に対して、「実効性」と「経済性」を兼ね備えたソリューションとして提供することで、「技術リーダー」として国際貢献を目指すことができれば、と考えます。
3)「経済安全保障」としての温暖化対策
温暖化対策はもはや環境問題にとどまることなく、エネルギー安全保障そのものである。
・課題:
中国が圧倒的なシェアを持つ太陽光パネルやEV用バッテリーといったグリーン技術のサプライチェーンに、日本が過度に依存することは、経済安保上のリスクとなる。
・あるべき形:
国内のグリーン産業への投資を大胆に進め、戦略物資のサプライチェーンの強靭化を図る必要がある。
そのためには、「脱炭素」を「産業競争力強化」と「雇用創出」に直結させるための(シン)イノベーションを政府主導で生み出すことが必須となる。
日本が温暖化対策で真の存在感を示すためには、トランプ・習近平の二極対立の枠組みに埋没しないことが基本となろう。
自国の国益と地球規模の公益を両立させる、実利とイノベーション技術に基づいた独自の道筋を打ち出すことが求められている。