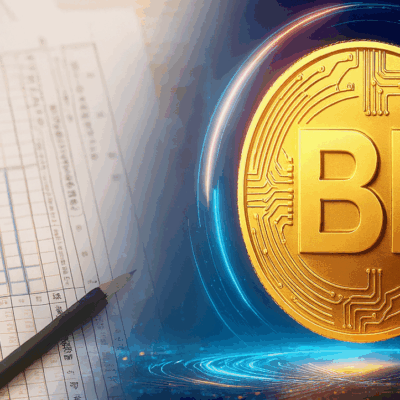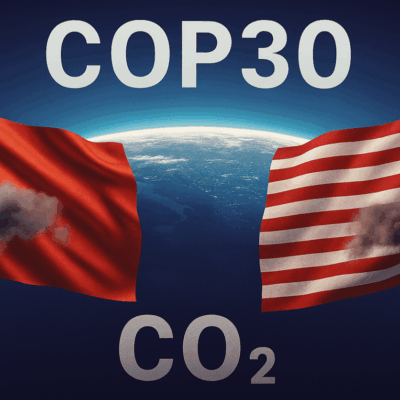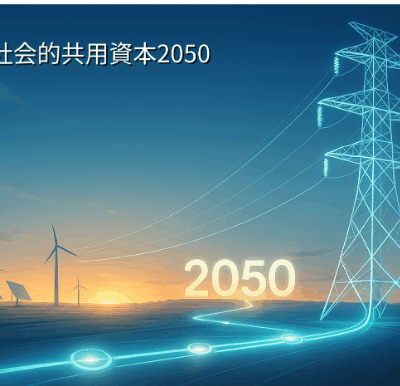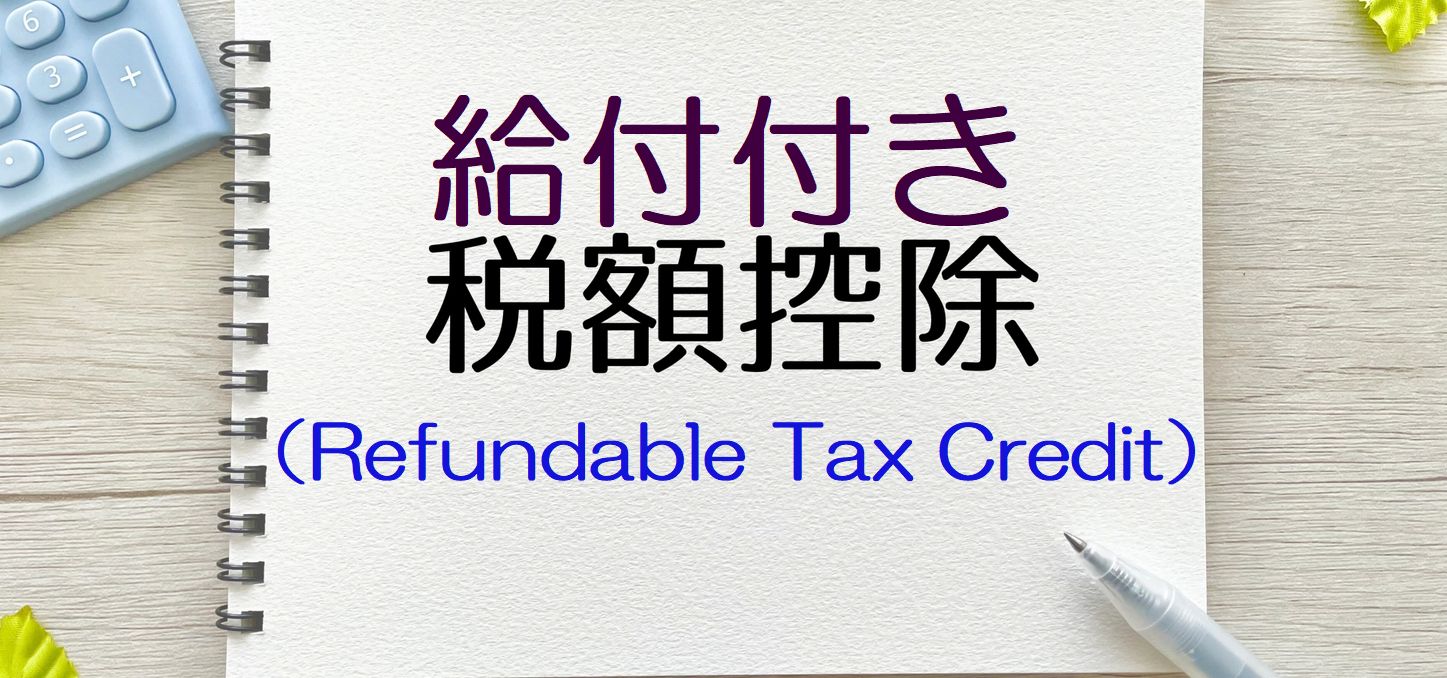
「全額給付制」へ移行した海外の教訓|給付付き税額控除の「煩雑さの罠」と日本独自の「シンBI」への道
給付付き税額控除制の課題、浮き彫りに
先に、名称と政治課題になっていることが浸透しつつある「給付付き税額控除」について、以下の記事を投稿しました。
⇒ 給付付き税額控除とは何か|制度の意義・課題・限界と「シン・ベーシックインカム2050」構想の展望 – ONOLOGUE2050 2025/10/16
そこでは、給付付き控除制の課題について整理し、近未来の構想としての日本独自のベーシックインカム、「シン・ベーシックインカム2050」の構想に置き換えることを提起しました。
その後、日経で、やはり、同制度の問題点を取り上げた、以下の記事が掲載されました。(同記事は、有料購読者のみ閲覧可能であることをご了承ください。)
⇒ 給付付き控除、海外も手探り 運用煩雑、英仏は全額支給に移行 現役世代限定の国も – 日本経済新聞 2025/10/24
同記事は、日経が先行して掲載した、2つの<経済教室>欄掲載の以下の記事をフォローした感があります。
⇒ (経済教室)給付付き税額控除の論点(上) 英国の制度 モデルに導入を 森信茂樹・東京財団シニア政策オフィサー – 日本経済新聞 2025/10/8
⇒ (経済教室)給付付き税額控除の論点(下) 情報連携インフラが基盤に 栗原克文・筑波大学教授 – 日本経済新聞 2025/10/9
そこで、先週10月24日掲載記事を整理してみました。
給付付き税額控除、海外も手探り|運用の煩雑さと対象設計が課題に
1.連立合意で実現へ機運高まる
自民党と日本維新の会は連立合意書で「給付付き税額控除」Refundable Tax Credit (RTC)の実現を明記した。
高市早苗首相も「早期に制度設計を進める」と意欲を示した。
参院選では維新、立憲民主、国民民主なども導入を公約に掲げ、9月には自民・公明・立民3党が海外事例を討議するなど、導入へ向けた機運が高まっている。
GTCは一般的に、所得税から一定額を控除し、引ききれない分を現金で給付する仕組みである。
2.海外事例は二極化:煩雑さから全額給付へ移行した国も
海外の事例は大きく以下の二つに分かれる。
1)全額給付へ移行した国(英国・フランス):
これらの国では、控除と給付を組み合わせてスタートした。
しかし、制度の煩雑さや雇用主・行政の事務負担の重さが問題となり、RTCから全額給付の仕組みに切り替えたとされる。
所得が毎年大きく変わる人々の捕捉が難しく、過誤支給(払いすぎや不正受給)の懸念が高まりやすかったことが背景にある。
2)控除と給付を維持する国(米国・カナダ):
これらの国ではRTCの仕組み=と給付の組み合わせを維持している。
共通しているのは国民全員が確定申告を行う文化があることだ。
所得の実態を正確に把握できる体制が、適正な控除や給付の土台となっている。
3.日本での課題|所得把握と申告文化の壁、低い確定申告率と現役世代支援の明確化
日本で確定申告をする人は約2300万人、国民の5人に1人にとどまる。
給与所得者(年収2000万円以下)には申告義務がなく、大半の会社員は源泉徴収や年末調整で済ませている。
過去には「全納税者に申告を義務化すべき」との提案もあったが、「個人の事務負担が増える」と反発が強く、全員申告制の導入は「個人の事務負担が増える」との過去の批判もあり、容易ではない。
4.制度設計の方向性:目的と対象の明確化
制度設計は政策目的によって異なり、その明確化が不可欠である。
以下がその例である。
・対象世代の明確化:
米国は25〜64歳、英国は18〜65歳を対象にするなど、現役世代への支援を明確にしている。
・勤労インセンティブ:
多くの国では勤労者を中心に据え、所得が上昇すると控除額が逓減する設計を採用し、勤労意欲を支援している。
日本では物価高や実質賃金低下、社会保険料の上昇により手取りが減少しており、働く世代の可処分所得を増やす施策が求められている。
5.なぜ今RTCなのか|一律給付・減税の限界と手取り減少への対策
日本では物価高に賃金上昇が追いつかず、実質賃金の減少が続いている。
また、高齢化による社会保険料の上昇が賃上げ効果を相殺する問題もあり、各党は現役世代の「手取りを増やす」施策を模索している。
一律の現金給付は「バラマキ」との批判が強く、住民税非課税世帯を対象にしても資産を持つ高齢者が含まれるなど公平性に欠ける。一方、所得税減税は中〜高所得者が中心に恩恵を受ける。
これに対し、給付付き税額控除は、税額控除と給付を組み合わせることで、控除のメリットが乏しい低所得の勤労世帯を的確に支援できる制度として注目されている。
まとめ|実現に向けた課題
海外では運用の煩雑さを克服できず全額給付に移行した国も多い。
一方で、確定申告文化を前提とした米加型モデルは精度の高い支援を実現している。
日本が制度を導入するには、所得・資産情報の正確な把握、地方自治体との連携体制の構築、制度の煩雑化回避と行政負担の軽減が課題となることから、シンプルで公平な設計を目指す必要がある。
加えて、前提として、目的の明確化が不可欠であり、「誰を・何のために支援する制度か」を定義づけることが鍵となる。
全額給付制度とは
上記要約の中で、給付付き税額控除制の導入後、「全額給付制度」へ移行した国があることが示されました。
「全額控除制度」とはどういう方式なのか、その理由を含めて整理しました。
「全額給付制度」とは、税額控除と給付金を組み合わせる仕組み(=給付付き税額控除)ではなく、最初から「現金給付だけ」で支援を行う制度のことです。
もともと給付付き税額控除は、
1)所得税を一定額控除し(減税)
2)控除しきれない分だけ現金で支給する
という「減税+給付」の二段構えでした。
ところが、イギリスやフランスのように運用してみると、
・所得や勤務形態が毎年変わる人の把握が難しい
・控除額と給付額を毎回計算するのが複雑
・雇用主や自治体の事務負担が増える
・所得申告のずれや過誤支給が頻発する
といった問題が生じました。
そのため、「いっそ税控除をやめて、対象者に直接現金を支給しよう」という方向に転換したのが「全額給付制度」です。
つまり、税計算に組み込むのではなく、行政が直接お金を渡す方式です。
具体的には、
・英国では「ユニバーサル・クレジット(UC)」に一本化し、所得に応じて現金を支給。
・フランスでも同様に、低所得層に対し税制を通さず給付を行う方式へ移行しました。
この方法のメリットは、
・手続きが簡単でスピーディー
・過誤や二重支給が減る
・対象を柔軟に設定できる
一方でデメリットとして、
・「減税による恩恵」との整合性がなくなる
・財源がすべて歳出(支出)扱いになる
などの課題もあります。
要するに、「全額給付制度」とは、税と給付を一体にせず、税控除の計算を省いて直接お金を配る簡素化モデルというわけです。
「給付付き税額控除」導入よりも先に行うべき改善・改革とその実現可能性の低さ
給付付き税額控除は、いわゆる「所得再分配」政策の一つです。
「所得再分配」の方法の一つとして導入し、結果として手取りを増やすということに。
しかし、その検討・導入前に取るべき対策は、まずは賃金の引き上げです。
但し、最低賃金法の法改正による以外は、基本的には、企業・事業主の経営政策に依拠するものであり、政府の関与は間接的で極めて限定的です。
従い、政治・行政において可能なのは、社会保険制度の見直し、主に富裕者層の対する所得税法の見直し、金融所得に対する課税法の改正など。
これらを「給付付き税額控除」Refundable Tax Credit (RTC)に先行して検討し、改正を図るべきでしょう。
これらの課題を解決することがいかに難しいかは、簡単に想像することができます。
従い、物価上昇を上回る賃金所得の上昇がない限り、穴埋め対策としての小手先の政策、近視眼的な法律改正を繰り返すことは目に見えている。
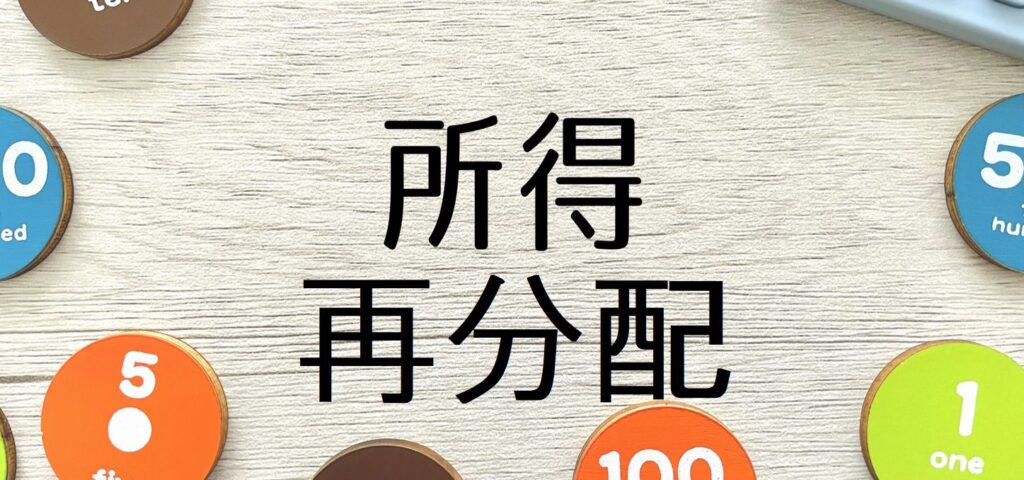
対象者限定ベーシックインカムをイメージさせる全額給付制度
UCとシンBIの役割の違い|UCはなぜ「シンBI」の答えではないのか
英国の「ユニバーサル・クレジット(UC)」は、全額給付モデルとして多くの給付制度を一本化し、RTCの課題を克服しようとした先進事例です。
しかし、UCも依然として「所得・就労状況による選別」を伴うため、煩雑な情報連携と、所得に応じた給付の「逓減・停止」計算を必要とします。
この点が、「無条件」と「すべての控除の廃止」を目指す私たちの「シン・ベーシックインカム2050」とは決定的に異なります。UCが「限定的なベーシックインカム」であるのに対し、シンBIは、全世代・全所得層を包摂し、税制・社会システム全体を簡素化する「抜本的な文化および社会経済システム改革」を意図しているのです。
RTCの議論は、日本がUCのような「限定的なBI」で立ち止まるのか、それともシンBIのような「根本的解決」へ舵を切るのかを問う試金石と言えます。
種々の煩雑さや不正リスクなどを回避するために結局採用することになった「全額給付制度」。
直接現金を給付するという制度と聞くと、世代や勤労状況などの条件付きではあっても、一種の「ベーシックインカム」ということができるのでは、と。
しかも、海外の例を見ると、主として「現役世代」を対象としています。
賃金所得者対象の制度なので当然ですが。
児童や高齢者への現金給付が社会保障制度の軸となっていることを考えると、世代間の競争原理から脱却して、全世代型社会保障制度の一環として評価できるものと考えます。
児童や高齢者が優先的にベーシックインカム給付を考えられる対象となりますが、ベーシックインカムを現役世代にも支給するというイメージが「全額給付制度」には含まれている。そう想定可能です。
全額給付制度に変化した給付付き税額控除制は、このようにベーシックインカムと親和性があることを確認できるかと思います。
あとは、就労する賃金所得者以外の、未就労者をどうするか、という課題が残ることになります。
ユニバーサル・ベーシックインカム(UBI)は、就労・未就労を問わず、すべての人々に支給するものです。
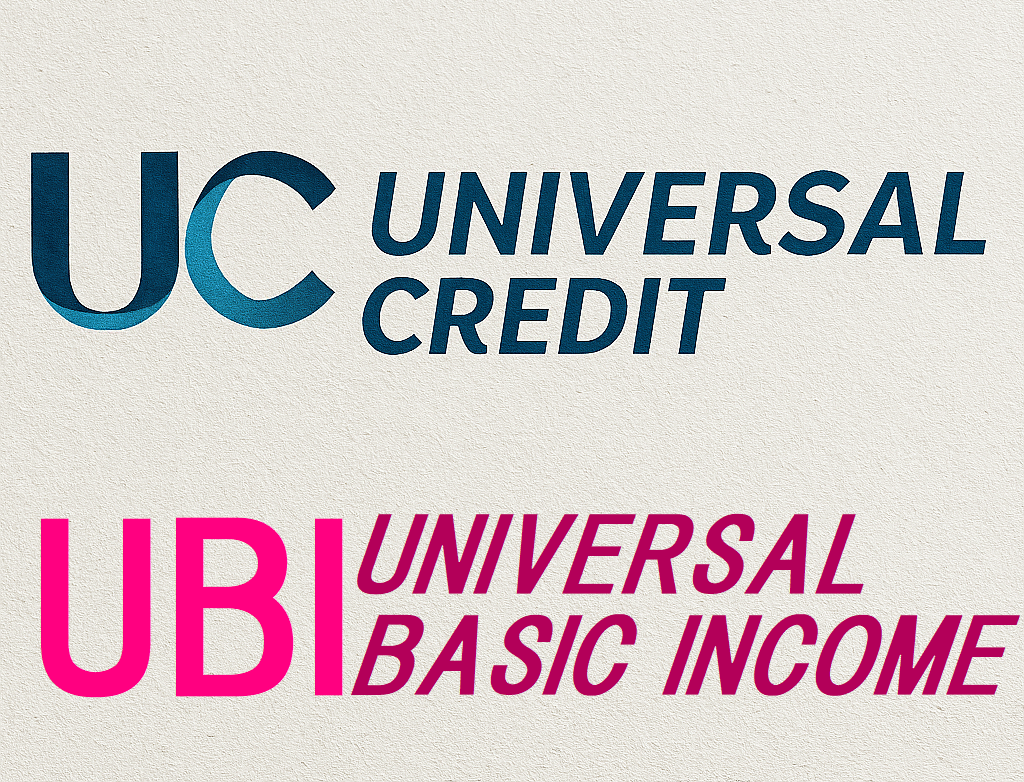
日本独自のベーシックインカム、「シン・ベーシックインカム2050」推奨論との関連から
冒頭で紹介した記事ですが、「給付付き税額控除」の導入よりも推奨したベーシックインカム。
これは、一般的なベーシックインカムとは全く異なり、関連する諸制度・法律の改正・改革を統合する「シン・ベーシックインカム2050」を提起するものでした。
⇒ 給付付き税額控除とは何か|制度の意義・課題・限界と「シン・ベーシックインカム2050」構想の展望 – ONOLOGUE2050
前項でも述べたように、RTCに取り組む前に、先に改正・改革すべき社会保障制度、社会システム、税制・財政改革などを考えべき。実は、シン・ベーシックインカム2050の理念と目的において、それらの課題を一括して、包摂して組み込むのです。
本稿のきっかけとなった、日経のRTCの課題の確認記事では、「課題は所得をいかに正確に把握するかだ。支給の実務面で地方自治体との連携も必要になる。」と結んでいました。
当然ですが、ベーシックインカムを意識したものではまったくありません。
そして、もっとも困難な課題である「所得の正確な把握」を挙げたのです。
その課題が、実は富裕層、高所得者層が最も警戒し、嫌うことであることを、どこまで認識しているか。
そして突き詰めれば、それらの層の所得税減税ではなく、RTC導入における財源確保のための増税に繋がる可能性が高いことを、しっかり認識しているか。
そこまでは言及していないことがその記事の根源的な問題と考えています。
【まとめ】 RTCは抜本的改革への「踏み台」か、それとも「立ち止まりの壁」か
本稿では、給付付き税額控除(RTC)が、英国やフランスで運用の煩雑さから「全額給付」へ移行した事実を、日経記事から確認しました。
これは、RTCが持つ「選別」と「税計算との連携」の複雑性が、行政コストと過誤支給のリスクを高めるという根本的な課題を抱えていることを示していました。
日本がRTCを導入する際には、米国・カナダ型のように「国民全員の確定申告文化」がないため、所得と資産の正確な把握という「情報の壁」が極めて高く立ちはだかります。
この課題は、富裕層・高所得者層が最も警戒する個人情報への踏み込みであり、RTCがその層の所得税減税策ではなく、財源確保のための増税に繋がる可能性が高いことを示唆しています。
RTCは、インフレ下の対症療法としては注目されますが、本来先に行うべき「社会保険料負担の見直し」や「富裕層への課税強化」といった構造的な改革を迂回する「小手先の政策」になるリスクを孕んでいます。
当サイトが提唱する「シン・ベーシックインカム2050」構想は、このRTCが持つ「選別の限界」「情報の複雑性」「財源論の呪縛」等の課題を克服し、「無条件給付」と「すべての控除の廃止」によって、よりシンプルで、真に持続可能な全世代型社会保障制度を目指します。
RTCの議論は、その是非を問うこと以上に、日本が抱える税制・社会保障制度の根本課題を国民に可視化させるという点で大きな意味を持ちます。
RTCが、抜本的改革である「シンBI」の実現には、別の観点から必要となる「情報インフラ整備の導火線」となるか、あるいは「複雑さに立ち止まる壁」となるか、その動向も注視し、引き続き考察と提案を進めていきます。

(参考):2022年提案日本独自のベーシックインカム「ベーシックペンション」試案記事
シン・ベーシックインカム2050は、2026年初めに明確な定義と構想、内容を提案する予定です。
現時点では、https://basicpension.jp で2022年に提案した以下の記事が、その基盤となるものです。
参考にして頂ければと思います。
・ベーシック・ペンション法(生活基礎年金法)2022年版法案:2022年ベーシック・ペンション案-1 – 日本独自のBI、ベーシック・ペンション
・少子化・高齢化社会対策優先でベーシック・ペンション実現へ:2022年ベーシック・ペンション案-2 – 日本独自のBI、ベーシック・ペンション
・マイナポイントでベーシック・ペンション暫定支給時の管理運用方法と発行額:2022年ベーシック・ペンション案-3 – 日本独自のBI、ベーシック・ペンション
・困窮者生活保護制度から全国民生活保障制度ベーシック・ペンションへ:2022年ベーシック・ペンション案-4 – 日本独自のBI、ベーシック・ペンション
当案をシン化させたシン版ベーシックインカム2050(ベーシックペンション2050)を2026年迄には作成・提案します。