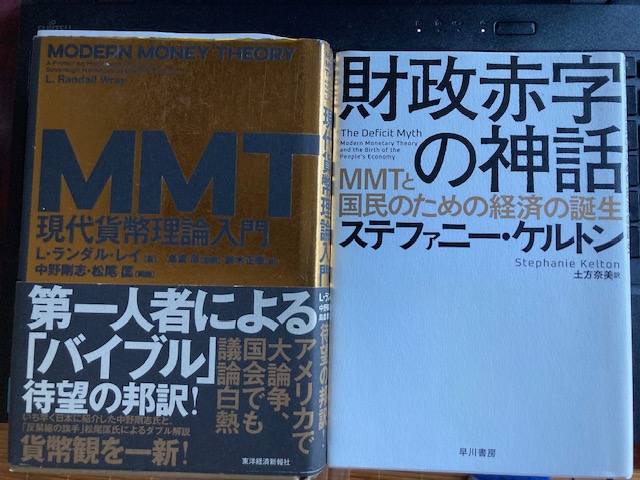シンMMT2050:日本社会構想を支える新たな財政・貨幣システムの羅針盤
第3章 シンMMT2050構想理念
はじめに
本稿は、「2050年日本社会構想」のための5つの主要な設計理念を掘り下げるシリーズ記事の第3章にあたります。
これまで私たちは、まず第一に、従来の軍事・防衛概念を超え、国民生活のあらゆる側面における「安心・安全・安定」を追求する基軸理念「シン安保2050」を提示してまいりました。
⇒ 2050年日本社会構想の基軸設計理念「シン安保2050」の意味と究極の使命 – ONOLOGUE2050
続く第2章では、故・宇沢弘文氏の「社会的共通資本」哲学を現代的に再構築し、すべての個人が尊厳を持って生きられる社会基盤を「共用」の概念のもとで再定義する「シン社会的共通資本2050」の意義と構想を詳述しました。
⇒ 2050年、日本社会の新たな羅針盤:『シン社会的共通資本2050』が拓く共生の近未来 – ONOLOGUE2050
「シン安保2050」が生活・人生基盤の多様な安全保障を、そして「シン社会的共通資本2050」がその普遍的な基盤の在り方を示す中で、これらの壮大な構想を実現するためには、確固たる財政的基盤が不可欠であることは明らかです。
本章では、この問いに応えるべく、現代貨幣理論(MMT)を日本社会に最適化し、規律ある運用を目指す「シンMMT2050」について考察します。
「シンMMT2050」は、単なる経済理論に留まらず、先の二つの理念、そして今後論じる「循環型社会2050」「シン・イノベーション2050」といった他の設計理念の実現に不可欠な、新たな貨幣・財政システムの在り方を提示します。
それは、従来の財政制約に囚われず、国(家)社会が主体的に未来への戦略的投資を実行し、国民のウェルビーイングを最大化するための羅針盤となるでしょう。
それでは、その内容と考え方を順に追っていきましょう。
第1節 MMTとは
本節では、現代貨幣理論(Modern Monetary Theory, MMT)の基本的な概念と、それが貨幣、財政金融、そして景気経済にどのように関わるのかを解説します。
1-1 MMTの概要
MMTは、「主権通貨を持つ政府は、自国通貨建ての債務を返済するために課税や債券発行による資金調達を必要としない」という考え方を中核とする経済理論です。
政府は通貨の発行者であるため、財政的な制約は存在せず、インフレの制約のみが存在するとMMTは主張します。
この理論は、失業者の存在を、政府が自国通貨を発行して必要な支出を行っていないことの証拠と見なします。
MMTの支持者は、政府支出は経済を活性化させ、完全雇用を達成するための主要な手段であると提唱します。
1-1-1 MMTの起源と主な提案者
MMTの思想的ルーツは、ジョン・メイナード・ケインズの有効需要の原理、G.F.ナップの国家貨幣説、ハイマン・ミンスキーの金融不安定性仮説、そしてアバ・ラーナーの機能的財政論といった、歴史上の様々な経済思想にまで遡ることができます。
現代のMMTとして体系化されたのは、主に1990年代以降、以下の経済学者たちによってです。
1)ウォーレン・モズラー (Warren Mosler):MMTの創始者の一人とされ、金融市場での実務経験から貨幣の本質に関する洞察を深めました。
2)ステファニー・ケルトン (Stephanie Kelton):MMTを最も著名な形で広めた一人であり、政策立案者や一般の人々に向けてMMTの考え方を積極的に発信しています。彼女の著書『財政の神話』はMMTを理解する上で重要な一冊です。
3)ランダル・レイ (L. Randall Wray):ポスト・ケインジアン経済学の視点からMMTの理論的基盤を構築し、多くの研究論文を発表しています。
4)ビル・ミッチェル (Bill Mitchell):オーストラリアの経済学者で、MMTの理論的発展と普及に大きく貢献しており、ブログなどを通じて活発な情報発信を行っています。
これらの学者たちは、既存の主流派経済学とは一線を画し、ポスト・ケインジアン経済学の一派として位置づけられます。
彼らは、貨幣が国家によって創造されるという「内生的貨幣供給論」を支持し、政府の財政政策の役割を重視するという点で共通しています。
1-2 貨幣論としてのMMT
MMTにおける貨幣観は、主流派経済学とは大きく異なります。
MMTは、「貨幣は国家が創出する負債であり、その価値は政府が徴収する税金によって裏付けられる」という考え方、すなわち「租税駆動説」(Tax-Driven Theory of Money)を採ります。
具体的には、政府が税金を徴収するために自国通貨を必要とさせることで、その通貨に対する需要が生まれ、価値が付与されるとMMTは説明します。
銀行は政府の支出によって創造された準備預金を基に、融資を通じて預金通貨を創造しますが、これはあくまで政府発行の通貨を「仲介」しているに過ぎないと考えます。
つまり、政府が通貨の最終的な発行者であり、通貨の価値の源泉である、という点が強調されます。
1-3 財政金融論としてのMMT
MMTは、財政政策が金融政策よりも経済調整において強力なツールであると考えます。
主権通貨を持つ政府は、通貨発行権を持つため、財政赤字を気にする必要がなく、むしろ景気刺激のために積極的に財政支出を行うべきだと主張します。
金融政策に関しては、MMTは金利の調整や量的緩和といった中央銀行の役割を、財政政策の補助的なものと位置付けます。
中央銀行は政府の支出を円滑にするための技術的な役割を果たすものであり、独立して金融引き締めを行うことは、政府の目標達成を阻害する可能性があると指摘します。
1-4 景気経済論・インフレリスク論としてのMMT
MMTは、インフレの主要な原因は、総需要が経済の生産能力(実物資源)を超過することにあると見なします。
つまり、貨幣供給量の増加そのものがインフレを直接引き起こすのではなく、労働力や原材料などの実物資源に制約がある中で、需要が過剰になった場合にインフレが発生するという考え方です。
したがって、政府支出は、インフレ圧力が発生するまで行うべきであり、インフレが顕在化した場合には、増税や支出削減といった財政的な手段を用いて需要を抑制すべきだと提唱します。
MMTは、完全雇用を達成しながらもインフレを抑制することを目標とし、そのバランスを取ることが重要であると考えます。
筆者の基本認識ー1|「シンMMT2050」のためのメモー1
次項のテーマと一部重なりますが、本稿執筆の私は、MMTが完全雇用と一体化していることには、反対しています。
また、MMTが経済活性化のためのものという限定・制約にも反対です。
すなわち、MMTを、景気刺激のために積極的に財政支出を行うためのものという前提条件にも反対です。
これらは、「シンMMT2050」の要点です。
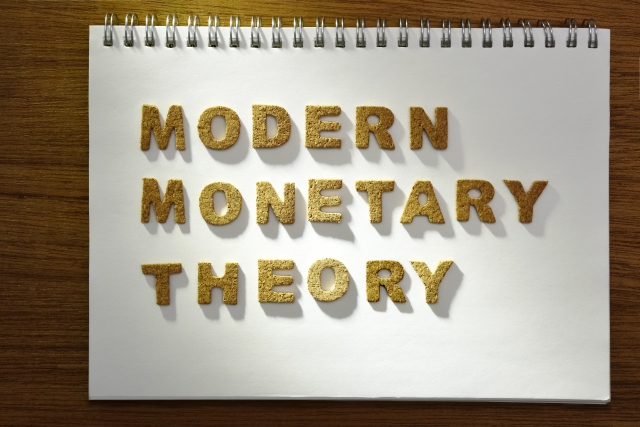
第2節 MMT批判とMMTの弱点
本節では、MMTに対する主要な批判と、MMT自体が抱える短所や課題について考察します。
2-1 MMT批判論の本質と評価
MMTは、その革新的な主張ゆえに、既存の経済学の枠組みから多くの批判を受けています。
2-1-1 財政規律論からの批判
最も一般的な批判は、「財政規律の欠如につながる」というものです。
MMTが財政赤字を問題視しないため、政府が無制限に支出を行い、無駄な公共事業やばらまき政策につながるのではないかという懸念が表明されます。
しかし、MMTはインフレ制約の重要性を強調しており、無制限の支出を推奨しているわけではありません。
2-1-2 インフレ論からの批判
前項と重なりますが、MMTのインフレに対する見解も批判の対象です。
貨幣供給量の増加が直接インフレにつながるという伝統的な貨幣数量説を支持する立場からは、MMTがインフレリスクを過小評価していると指摘されます。また、実物資源の制約がどの時点で発生し、インフレに転じるのかという判断の難しさも課題として挙げられます。
2-1-3 国際収支・為替レート論からの批判
小国開放経済においては、無制限の財政支出が自国通貨の信認低下や為替レートの急落、輸入インフレを引き起こす可能性が指摘されます。MMTは主権通貨を持つ政府に焦点を当てますが、特に国際的な資本移動が活発な現代においては、この点が弱点と見なされることがあります。
2-1-4 その他
MMTが提唱する「政府による雇用保障プログラム(Job Guarantee)」についても、その実施可能性や効率性、労働市場への影響などに関して議論があります。
2-2 公共貨幣論との違いと課題
MMTと類似の概念として「公共貨幣論(Public Money Theory)」が挙げられますが、両者には重要な違いがあります。
2-2-1 公共貨幣論
中央銀行が直接政府の財政支出に必要な貨幣を発行し、その貨幣を政府が支出することで、民間銀行を介さずに貨幣が供給されるという考え方です。これは、銀行の信用創造を否定し、貨幣発行権を政府または中央銀行に限定することで、金融システムをより公共的に管理しようとする試みです。
2-2-2 MMTとの違いと課題
MMTは、現在の銀行システムと中央銀行の役割を基本的に維持した上で、政府の財政政策の自由度を拡大しようとします。
一方、公共貨幣論は、既存の貨幣システムそのものを根本的に変革しようとします。
この違いから、公共貨幣論はより急進的な変革を伴い、金融システム全体に与える影響も大きいという課題を抱えます。
MMTは、既存の金融システムを活かしつつ、その運用思想を変えることで、目標達成を目指すという点で、より現実的なアプローチと見なされることがあります。
(参考)
⇒ 投稿を編集 “公共貨幣論の限界を乗り越えるベーシック・ペンション論構築へ:公共貨幣論から考える-20(総括・活用編)” ‹ 日本独自のBI、ベーシック・ペンション — WordPress 2022/7/31
2-3 MMTの短所・弱点と課題
MMT自体が抱える短所や課題も存在します。
2-3-1 理論の実証的根拠の不足
MMTの主張は、理論的には整合性があるものの、大規模な経済圏での実証例が少ないため、その有効性や予見性に対する疑問が残ります。特に、インフレを抑制しながら長期的に完全雇用を維持できるかについては、さらなる検証が必要です。
2-3-2 政治的な実装の困難さ
MMTの政策提言、特に大規模な財政支出や雇用保障プログラムは、既存の政治・経済システムや財政規律の考え方と相いれない部分が多く、政治的な合意形成や実装が極めて困難であるという課題があります。財務省や中央銀行、既存政党の意識改革が不可欠となります。
2-3-3 インフレ判断の難しさ
MMTはインフレが実物資源の制約によって生じると主張しますが、その制約がどこにあるのか、また、いつインフレに転じるのかを正確に判断することは非常に困難です。インフレの発生を見誤ると、経済に深刻な打撃を与える可能性があります。
2-3-4 グローバル経済における影響
MMTの議論は主に自国通貨を持つ国に焦点を当てていますが、グローバルに統合された経済において、他国の経済状況や国際的な資本移動が自国経済に与える影響を十分に考慮できていないという指摘もあります。
筆者の基本認識ー2|「シンMMT2050」のためのメモー2
本項に提示された「政府による雇用保障プログラム(Job Guarantee)」に関しては、完全雇用と同義であり、私は反対しています。
代わって提唱しているのが「日本独自のベーシックインカム(BI)、ベーシックペンション(BP)」の全国民への支給です。
「シンMMT2050」とは直接関連はありませんが、財源論とは共通性を持つので、ここでメモを加えておきました。

第3節 日本におけるMMTの理解度・認知度と壁
本節では、まず筆者のMMTへの関心と「シンMMT2050」の構想に至る背景を述べます。
その上で、日本の社会におけるMMTの理解度、そしてその受容を阻む「壁」について、具体的なアプローチや既存の議論を交えながら深掘りしていきます。
はじめに|MMTへの関心と「シンMMT2050」構想へのリンク
私がMMTに関心を抱くようになったきっかけは、長年検討・提唱してきたベーシックインカム(BI)の考察に端を発します。
具体的には、「文化および社会経済システムとしての日本独自のベーシックインカム、ベーシックペンション」を掲げたウェブサイト「basicpension.jp」の運営を通じて、その財源確保の課題に向き合ったことが出発点でした。
これまで、このウェブサイトでは、日本語訳『MMT現代貨幣理論入門』に解説を寄せた松尾剛志氏の著書『世界インフレと戦争』や、同書の監訳者である島倉原氏の著書『MMTとは何か』を題材としたシリーズ記事を掲載してきました。
また、MMT論者である井上智洋氏の著書『「現金給付」の経済学』シリーズや、スコット・サンテンス氏の『Let There Be Money』シリーズも紹介し、MMTの多様な側面を考察してきました。
さらに、山口薫氏の著書『公共貨幣』や『公共貨幣入門』を題材としたシリーズも投稿し、MMTと関連する貨幣論についても疑問を少しでも払拭したいと取り組んできました。
(参考)
⇒ 公共貨幣論の限界を乗り越えるベーシック・ペンション論構築へ:公共貨幣論から考える-20(総括・活用編) – 日本独自のBI、ベーシック・ペンション
⇒ 社会経済システムそして日本の文化としてのベーシック・ペンションの実現へ:【『世界インフレと戦争』から考える2050年安保とベーシック・ペンション】シリーズー11(最終回) – 日本独自のBI、ベーシック・ペンション
⇒ 民主主義頼みのMMTをベーシック・ペンション提案にどう活用するか:島倉原氏著『MMTとは何か』から考えるベーシック・ペンションー8 – 日本独自のBI、ベーシック・ペンション
⇒ 脱成長vs反緊縮と経済第一主義とベーシックインカム:井上智洋氏著『現金給付の経済学 反緊縮で日本はよみがえる』から考える-6 – 日本独自のBI、ベーシック・ペンション
⇒ スコット・サンテンス氏の想いを知る:『ベーシックインカム×MMTでお金を配ろう』から考えるベーシック・ペンション-1 – 日本独自のBI、ベーシック・ペンション
これまでこうした考察を通じて、MMTが日本の近未来に必要な公共政策の財政基盤となり得る可能性に、いやむしろそうすべきという考えに至ったのです。
特に、デジタル通貨の活用による貨幣の循環とガバナンスおよびマネジメントシステム、インフレリスクへの対策に関する検討は、MMTの理論を現実社会に適用する上での課題克服に繋がると考えています。
今回の「シンMMT2050」は、これらの考察を発展させ、「シン社会的共通資本2050」や「シン安保2050」といった他の公共政策に必要な基礎財源としても機能する、全く新しいMMT概念と理念、すなわち「シンMMT2050」を設定することを目指しています。
これは、従来の財政制約にとらわれず、日本の将来に必要な公共事業および公共サービスと多様な安全保障を盤石なものとするための、新たな財源・財政基盤を提示する試みです。
3-1 財源・財政論アプローチと「租税国家」の壁
日本におけるMMTの議論は、しばしば財源論や財政問題へのアプローチとして捉えられます。
その代表的な論者の一人として、中野剛志氏が挙げられます。中野氏は、日本のデフレ脱却や経済成長のために、政府が財政支出を拡大すべきだと主張し、その財源としてのMMTの考え方を積極的に紹介しています。
このアプローチは、緊縮財政の弊害を指摘し、積極財政への転換を訴える点で、MMTの主要な論点と合致します。
しかし、既存の財政健全化路線や国債発行への抵抗感が根強い日本では、財源は課税で賄うべきという「租税国家」の意識が強く、MMTが提唱する「自国通貨建て債務に財政制約はない」という考え方は、無責任な財政拡大論として批判に晒されがちです。
L・ランダル・レイ氏が指摘するように、「人々の直感は、『税金で支出を賄う』というメタファーを好む」傾向があり、この「文化的遺伝子」とも言える意識が、MMTの理解を阻む大きな壁となっています。
3-2 所得再分配論アプローチと本質理解の課題
MMTは、インフレにならない範囲での政府支出拡大によって経済を活性化させ、結果として所得の再分配機能を強化するという側面があります。
例えば、公共事業や社会保障関連の支出拡大は、低所得者層や不安定な雇用に置かれる人々への所得移転となり、経済的格差是正に寄与すると考えられます。
このアプローチは、経済的格差の拡大が社会問題となる中で、MMTが格差是正の手段として有効であるという視点を提供します。
しかし、単なる所得再分配論としてMMTが語られる場合、その本質である貨幣観や財政金融論の理解が置き去りになる可能性も指摘されます。また、再分配の具体的手法やその効果の持続性については、さらなる議論が必要です。
3-3 ベーシックインカム論アプローチ
前述の通り、筆者がMMTに関心を持つきっかけとなったのが、ベーシックインカム(BI)の財源論です。
BIは、全ての人々に無条件で一定額の所得を給付する制度であり、その安定的な財源確保が常に大きな課題となります。
MMTの考え方、すなわち自国通貨建てで政府が支出を行うことに財政的な制約はないという理論は、BIの恒久的な財源として極めて魅力的に映ります。
しかし、BI論者の間でも、MMTの理解度は様々です。
MMTを単なる「打ち出の小槌」のように捉え、インフレリスクや実物資源の制約を軽視する議論も見受けられます。BIの実現可能性を高めるためには、MMTの本質を深く理解し、そのリスク管理も含めた包括的なシステム設計が不可欠です。
特に、リベラルを名乗る人や生活保護制度の絶対遵守を唱える人、社会保障制度を最重要視する専門家・学者研究者ほど、MMTへの関心と認識が薄く、財政規律主義と所得再分配主義を固執していることが意外です。
3-4 既存政党の財政認識と課題
日本の既存政党の多くは、依然として財政健全化目標を重視し、国債発行残高の増大を問題視する認識から抜け出せていません。
与野党問わず、財源論では増税や歳出削減が議論の中心となり、MMTが主張する「自国通貨建て債務は問題ではない」という考え方は、財政規律を緩めるものとして警戒されています。
しかし、最近の傾向として、特に野党の一部には積極財政を主張する動きが増えてきています。
今般の参院選でも見られたように、物価高対策としての給付や減税政策、デフレ脱却や経済成長を掲げ、政府の財政出動を求める声が大きくなっています。
ただ、この場合の財源は、富裕層からの所得再分配や投資収益課税といった「あるところから取る」アプローチに求める例が多く、一部では一般の所得税法改正を掲げていることも特徴です。
これは、国債増発への直接的な抵抗感は以前より低下していることを示唆しますが、MMTが提唱するような抜本的な財政観の転換、すなわち「自国通貨建て債務には財政制約がない」という共通認識に基づく財政規律をめぐる合意形成は、まだまだ遠いと言わざるを得ません。
その要因においては、長年のデフレ下でも財政赤字が拡大し続けたことへの懸念、あるいは将来世代への負担転嫁という倫理的な問題意識に根差している部分が大きいでしょう。
財政学者・小黒一正氏の「財政の民主的統制は難しい」という議論も、この背景にある国民的懸念を反映していると考えられます。MMTの理解を広げ、政策に反映させるためには、これらの既存の財政認識に対する根源的な問い直しと、国民的な合意形成が大きな課題となります。
3-5 日本のMMT論者の限界と課題
日本においてMMTを支持する論者は増えていますが、その議論にはいくつかの限界も存在します。
3-5-1 理論的深掘りの不足
MMTは貨幣の性質、銀行の信用創造、政府の役割など、多岐にわたる理論的背景を持ちますが、日本では一部の論点が先行し、全体の体系的な理解が十分でない場合があります。特に、インフレメカニズムや実物資源制約に関する議論の深掘りが求められます。
3-5-2 実践的政策提言の具体性不足
MMTの導入は、既存の社会システムや法制度の抜本的な見直しを伴います。しかし、具体的な移行プロセスや、それによって生じうる副作用への対処方法など、実践的な政策提言が具体性を欠くことがあります。
3-5-3 コロナ禍における特別定額給付金をめぐる浅薄なベーシックインカム論とMMT傾斜
日本のMMT論者の一部は、財政支出機能のみを取り上げて、2021年から22年にかけての新型コロナ禍における特別定額給付金と明け併せて、ベーシックインカムの導入を強く主張しました。
この一時金支出をもって、BI議論に持ち込んだ浅薄さには当時あきれ返ったものです。
案の定、この案件が終わり、コロナが終息に向かってからは、彼らの行動はピタッと止まってしまい、現在も思考・行動停止状態のままです。
またこの時、緊縮財政の打破を標榜してMMTとBIとをセットで提案した経済学者も、このところの物価対策のための給付金騒動では、ほとんど前面には出てきておらず、影が薄い状況です。
3-5-4 既存勢力との対話不足|
財務省、日本銀行、主流派経済学者、既存政党といった、財政・金融政策に大きな影響力を持つ既存勢力との建設的な対話が不足している点が挙げられます。
彼らの懸念や批判に真摯に向き合い、具体的な解決策を提示する姿勢が、MMTの社会実装には不可欠です。
島倉原氏が指摘する「MMT財政論が主流派経済学を論駁できない事情」も、この対話の難しさの一因を示唆しています。
ただ、現実としては、対話云々よりも、MMT批判論者を説伏・説得する方策を見いだせていないといった方が的を射ているというべきかもしれません。
筆者の基本認識ー3|「シンMMT2050」のためのメモー3
単純に、経済成長目的、緊縮財政反対、インフレ不安対策という視点だけからMMTを主張するのが手詰まり状態にある。
そう認識すべきでしょう。
そういう意味でも「シンMMT2050」という新しい概念と理念を構築する必要がある。
そういう基本認識で、本論・本稿、当サイト運営に取り組んでいます。

第4章 MMTのガバナンスとマネジメント
MMTを日本社会に実装し、その効果を最大限に引き出すためには、単なる理論の受容だけでなく、それを適切に運用・管理するためのガバナンスとマネジメントの仕組みを構築することが不可欠です。本節では、そのための課題と方策を探ります。
4-1 財務省・経済学者・政党をどう乗り越えるか
MMTの思想を日本に根付かせる上で、最も高い壁となるのが、既存の財務省、経済学者、そして政党の意識と構造です。
4-1-1 財務省
長年、財政規律を重視し、歳出削減と増税を主導してきた財務省の存在は、MMTが提唱する「財政制約はない」という考え方と真っ向から対立します。
彼らの持つ権限、情報、そして専門性を考慮すれば、その認識を変革し、MMTに基づいた財政運営へと転換させることは極めて困難な挑戦です。彼らを「敵」と見なすのではなく、国の長期的な利益という共通目標のもと、建設的な対話を通じて理解を深めていくアプローチが必要です。
4-1-2 経済学者
主流派経済学の教育を受け、長年そのパラダイムの中で研究を続けてきた多くの経済学者にとって、MMTの革新的な貨幣観や財政観は受け入れがたいものです。
彼らの多くは、政府の債務問題やインフレリスクを強く懸念しており、MMTを非現実的あるいは危険な思想と見なす傾向にあります。
しかし、島倉原氏が指摘するようにMMTが「現実とも整合的」であるという主張を前提としつつも、主流派経済学者の懸念に真摯に向き合い、アカデミアにおけるMMTの本格的な研究と議論を促し、共通認識を構築していくことが求められます。
4-1-3 政党
既存政党は、選挙を意識した短期的視野に陥りがちであり、また財政規律という「常識」から逸脱することに躊躇します。
MMTに基づく政策は、有権者への説明も難しく、既得権益との摩擦も生じやすいため、これを政治課題として真剣に取り組む政党は限られています。
短期的視野に陥りがちな政党に対し、MMTが日本社会にもたらす長期的なメリットを提示し、国民的な議論を喚起することで、政党がMMTを政策の選択肢として真剣に検討せざるを得ない状況を作り出す必要があります。
これらの壁を乗り越えるためには、理論的な説明だけでなく、MMTが日本社会にもたらす具体的なメリットを提示し、国民の理解と支持を広げることが不可欠です。
以上も、前節と同様、一般論的な記述にとどまっていることは承知しています。
4-2 中央銀行の機能と政府財政との関係、そして新たな規律
4-2-1 中央銀行の役割
MMTにおいては、中央銀行の役割は、政府の財政支出を円滑にするための技術的な存在として位置づけられます。
具体的には、政府が国債を発行する際、中央銀行がそれを買い入れ、政府の口座に資金を供給することで、政府支出を可能にするというメカニズムが想定されます。
これは、中央銀行の独立性を重視し、政府の財政に直接関与すべきではないという従来の考え方とは一線を画します。
MMTの下では、中央銀行は金利の管理を通じて市場の流動性を維持し、インフレ目標の達成を支援する役割を担います。
しかし、政府の財政運営と中央銀行の金融政策が一体となることで、中央銀行の独立性が損なわれ、政治的な圧力によって無制限の貨幣発行が行われるのではないかという懸念も存在します。
したがって、「シンMMT2050」においては、中央銀行と政府の間に明確な役割分担と協調体制を構築し、インフレ抑制のための監視機能やガバナンスをいかに確保するかが、極めて重要な課題となります。
4-2-2 「シン循環貨幣MMT」のガバナンスへの貢献
次節第5節で定義する「シン循環貨幣MMT」(規律ある信用創造と貨幣の回収・消却メカニズム)こそが、中央銀行と政府が連携しながら、政治的裁量にのみ依存しない、新たな形の財政規律とマネジメントを可能にします。
この循環貨幣システムは、支出の目的、期間、回収方法等をあらかじめ設計することで、貨幣の過剰な滞留を防ぎ、実体経済の必要性に応じた健全な貨幣供給を維持する基盤となります。
4-2-3 日本銀行法・銀行法改革の意義
行き過ぎた金融市場主義や過剰流動性によるバブル発生を防ぐため、預金準備制度・準備率の法改正など、中央銀行と市中銀行の役割と責任を再定義する制度改革の必要性を論じます。
これは「公益民主主義」を支える経済システムとしてのガバナンスの一環として位置づけられ、『世界インフレと戦争』最終回で言及された課題に対応し、「シンMMT2050」のガバナンスを強化する上で不可欠であると考えます。
筆者の基本認識ー4|「シンMMT2050」のためのメモー4
本節において、日銀による国債発行が、MMTの財源調達方法であるとされています。
しかし、「シンMMT2050」では、国債発行によるものでなく、純粋に、専用デジタル通貨を貨幣発行権を利用して、政府に代わって日銀が発行し、管理する方法を採用します。(次節で後述)
日銀がこのデジタル通貨発行益を発行時に得る形を取り、発行されたデジタル通貨を、国の要求に従い国庫に送金します。

第5節 シンMMT2050の要素と本質
「シン安保2050」「シン社会的共通資本2050」、そして次のテーマ理念である「シン循環型社会2050」「シン・イノベーション2050」といった、望ましい2050年の日本社会を創造するための公共的政策の財源基盤として、私たちは「シンMMT2050」を位置づけます。
本節では、その具体的な要素と本質について掘り下げます。
5-1 シンMMTの条件
「シンMMT2050」は、単に従来のMMTの輸入ではなく、日本の社会構造や近未来像に即した新たな条件を付与することで、その有効性と持続可能性を形成します。
5-1-1 循環型社会経済の基幹としてのMMT
「シンMMT2050」は、近未来の日本社会が目指すべき循環型社会経済の基幹として機能することを条件とします。
これは、単に経済成長を追求するだけでなく、資源の持続可能性、環境との共生、そして社会の公正性を重視する経済システム全体を支える財政・金融の枠組みとしてMMTを捉えるものです。
「シンMMT2050」による財源確保・財源執行は、再生可能エネルギーへの大規模投資、廃棄物ゼロ社会の実現に向けたインフラ整備、地域循環型経済の活性化など、循環型社会への移行に必要な公共投資を可能にします。
この際、支出の対象は、短期的には、災害復興・災害復旧など緊急を要する事案に限定し、景気刺激策のような施策への支出は極力排除します。
そして、長期的な社会の持続可能性と広範な「安心安全安定・保持保有確保(安保)」に資する分野に、公共事業投資として優先的に投入することを基本とします。
5-1-2 貨幣創造権に基づく「シン循環貨幣」の本質
「シンMMT2050」の核心は、国債発行による資金調達に依存するものではなく、国家が有する貨幣創造権を行使して、目的と規律を持った形で貨幣を直接発行する点にあります。
そして、この貨幣は、単に数量が増えるだけでなく、社会の中で目的を伴って「循環」することを前提とします。
この「シン循環貨幣」は、例えば、特定の公共事業の費用、社会保障関連の給付、あるいは有限資源向け戦略物資の国内生産・調達支援など、「公共」「公益」に資する特定の目的に使途が限定されることを基本とします。
また、その使用状況をデジタル技術で追跡管理し、一定期間の利用を経て自動的に回収・消却されるメカニズムを内包します。
これにより、発行された貨幣が経済全体に健全に流通し、目標達成に貢献しつつ、無秩序なインフレを抑制する新しい管理モデルを構築します。
次の「シン循環型社会2050」の血液・血流の機能を果たすと言えるでしょう。
5-1-3 「シン循環貨幣MMT」への変革|支えるデジタル通貨
「シンMMT2050」のもう一つの重要な条件は、貨幣が社会の中で「循環」し、特定の目的のために使われることを促進する「シン循環貨幣MMT」への変革です。
加えて、この貨幣は国内だけで流通循環する制約があります。これを支えるのが、専用デジタル通貨の活用です。
専用デジタル通貨を活用することで、特定の公共政策(例:環境投資、地域活性化事業、戦略的産業支援)のために発行された貨幣の使用使途を制限したり、有効期限を設けたりすることが可能になります。
これにより、単なる貨幣量の増加によるインフレリスクを抑制しつつ、必要な分野へ確実に資金が投入され、社会全体の目標達成に貢献する貨幣の流れを創出することができます。
これは、貨幣を単なる「価値の尺度」や「交換手段」としてだけでなく、社会の目標達成を促す「ツール」として積極的に活用する試みです。
また、この国内のみ通用する特殊なデジタル通貨は、外為市場では流通しないことで、国際的な為替変動リスクから国内経済を保護し、安定した経済運営を可能にします。
将来的には中央銀行が発行する共通デジタル通貨(CBDC)との連携も視野に入れます。
但し、このCBDCとは別種の特別なデジタル通貨です。仮称として、(特別)公共事業デジタル通貨(Public Utilities Degital Currency:PUDC)とします。
5-1-4 「シン循環貨幣MMT」の対象領域の構想と研究継続
ここまでの検討において、「シン循環型貨幣MMT」活用領域が、少しずつ具体化されつつあります。
まず、国家及び自治体が保有する国有・公有資源の維持管理などのための支出があります。
土地建物・公共施設などが対象であり、基本的には複式簿記での資産管理案件です。
一部資産については、減価償却会計処理を行います。
大規模災害被災時の復旧コストの一部もシンMMTの使途となりますが、この時も厳正な経理会計処理が不可欠です。
一つの試案ですが、個人所有の家屋の立て直し資金も、このシンMMTから支出し、一次家屋は公有(資産計上)名義とし、利用権を個人に供与するという方式も検討の余地があると思います。
その他、デジタル通貨の回収方法として、社会保険料・税金の納付用として利用可能とすることも検討可能です。
また、公務員や準公務員の給与の一部を、公共費用・公益費用としてシンMMTから支出するなども検討可能でしょう。
今後の検討・研究課題とします。
5-2 シンMMT2050化の背景
「シンMMT2050」への移行は、既存の財政認識の限界を打破し、日本の近未来を切り拓くための必然的な選択です。
5-2-1 財政規律主義からの脱却プラン
長らく日本を縛ってきた「財政規律主義」からの脱却は、「シンMMT2050」の実現に不可欠な前提です。
これは、単に財政赤字を容認するということではなく、財政規律の「目的」を「国の健全な発展と国民生活の向上」に再定義するものです。
国債残高の多寡ではなく、インフレ率、失業率、実物資源の稼働状況といった実体経済の指標を基準として財政運営の是非を判断する「機能的財政論」の考え方を徹底します。
具体的な脱却プランとしては、メディアや教育を通じた国民への啓発、財政の専門家や政策立案者に対するMMTの基礎知識の徹底、そして何よりもMMTに基づいた成功事例の創出が挙げられます。
5-2-2 現状のMMTの信任度・理解度の壁打破プラン
現状、MMTは日本ではまだ一部の論者の間でしか十分に理解されておらず、多くの国民や政策決定者からの信任も得られていません。この信任度・理解度の壁を打破するための戦略が必要です。
具体的には、MMTの単純な賛美ではなく、その限界やリスクを正直に認め、それらへの具体的な対処法を明確に提示することが重要です。
また、海外におけるMMT関連の議論や、実際にMMT的発想で政策を実行した国・地域の事例(成功・失敗含め)を丁寧に紹介することで、議論の幅を広げ、理解を深める努力も必要です。
専門家だけでなく、一般市民にも分かりやすい言葉でMMTの本質と可能性を伝えるための、多角的なコミュニケーション戦略が求められます。
5-2-3 財政規律
「財政規律」は、国家財政の健全性を保つ上で確かに重要です。
しかし、「シンMMT2050」における財政規律は、従来の「国債残高対GDP比」といった形式的な指標に縛られるものではありません。
むしろ、「インフレ率の安定」「希望者完全雇用の達成」「実物資源の有効活用」「環境負荷の低減」といった、より実体経済に即した目標を達成するための「機能的規律」へと再定義されます。
これは、政府が自国通貨を発行できるという貨幣主権の事実を前提としつつも、無責任な財政運営を推奨するものではありません。インフレが加速する兆候が見られれば、増税や支出削減といった適切な財政調整も行うことで、経済の安定を図るのが「シンMMT2050」における真の財政規律です。
こう書きましたが、これは、一般論としての「シンMMT2050」論においての記述ですが、こうした固定的な視点での再定義から少し距離を置き、これから「シン」と「2050」に相応しい定義の形成を行っていきます。
5-3 シンMMT2050の定義と本質
上記の要素を踏まえ、「シンMMT2050」は、「危機に強く、安心安全安定・保持保有確保(安保)を追求し、持続可能な社会経済システムを構築するための、日本独自の新しい貨幣・財政理論と実践の枠組み」と定義します。
この定義が示すように、「シンMMT2050」は、MMTの貨幣観・財政観を基盤としつつも、日本の現実と近未来の課題解決に向けて独自に進化させた包括的な構想です。その本質を構成する主要な要素は以下の通りです。
5-3-1 規律ある信用創造と「シン循環貨幣MMT」
無制限な貨幣発行ではなく、国益と公益のために必要な規模で貨幣(デジタル通貨)を創造し、その循環と回収(消却)のメカニズムを組み込むことで、財政規律とインフレ抑制を両立させる、日本独自の貨幣マネジメントシステムを確立します。
5-3-2 租税の役割の再定義と機能的税制の追求
税金が財源ではなく、経済の調整弁、インフレ抑制、貨幣回収の手段であることを明確化します。
島倉原氏が指摘した「悪い税」(社会保障税、消費税、法人税など)の議論も踏まえ、「シンMMT2050」では社会の状況と目的に応じた機能的税制のあり方を志向します。
5-3-3 国内供給力と経済安保の強化
地政学的リスクの増大に対応するため、食料、エネルギー、半導体などの戦略物資の国内生産能力を強化し、必要に応じて特定の財に戦略的価格統制を行うことで、供給制約型インフレと外部からの脅威に対応する強靭な経済基盤を築きます。
5-3-4 「公益・公共民主主義」の追求
貨幣が国民の「公益」「公共」のために創造され、循環し、使われるという、国民と政府の間の新しい信頼関係と政治的ガバナンスのあり方を確立します。
L・ランダル・レイ氏が提唱する「選挙で選ばれた議員による、透明性と説明責任を備えた優れた予算編成」の実現は、この構想の不可欠な要素として位置づけられます。
5-3-5 「悲観的積極主義」ではなく「可能性実現積極主義」
MMT論者である中野剛志氏は、MMTを「悲観的積極主義」と表現しました。未来が不確実で困難を伴うことを直視しつつも、それらを乗り越え、より安心で豊かな社会を築くための、前向きで能動的な国家・国民の姿勢がこの構想の根底に流れる哲学としてでした。
しかし、当「シンMMT2050」は、「悲観性」を横に追いやり、「可能性実現」を積極的に追及する「可能性実現積極主義」を掲げます。
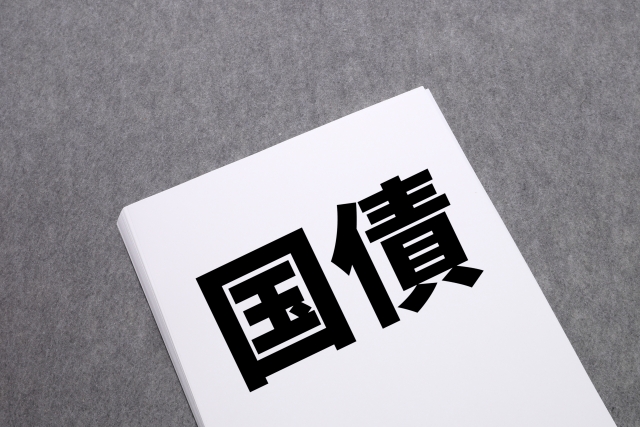
第6節 シンMMT2050と他の4つの設計理念との関係性
「シンMMT2050」は、単独で存在する理念ではありません。
それは、私たちが目指す望ましい2050年の日本社会を創造するための他の主要な設計理念 ――「シン安保2050」「シン社会的共通資本2050」「シン循環型社会2050」「シン・イノベーション2050」―― の財源・財政基盤として機能します。
本節では、「シンMMT2050」がこれらの理念の実現にいかに不可欠であるかを具体的に関連付けて論じます。
6-1 「シン安保2050」の財源・財政基盤としての「シンMMT2050」
「シン安保2050」は、従来の軍事・防衛に偏重した安全保障の枠を遥かに超え、というか、ある意味まったく異質で広範な「安心安全安定・保持保有確保」という概念を包摂します。
これは、エネルギー、食料、半導体といった狭義の具体的経済安保から、国民生活・市民生活や地域社会の安定、国家防衛、財政の安定に至るまで、多岐にわたる「安保」課題への対応を意味します。
「シンMMT2050」の貨幣・財政システムは、これらの広範な「安保」課題を解決するための財源を、既存の税収に依存せず、安定的に供給することを可能にします。
例えば、災害に強い国土強靭化や日常生活の安全のためのインフラ整備、水資源の保全、被災市民の生活復興、国民の困窮・健康の維持、医療・介護の持続性確保、公共事業の安定的・継続的実行など。
「シン安保2050」が掲げる「生活保障としての安全保障」「リスク回避と対応、安全への転換に必要な大規模な公共投資」を、財政制約に縛られることなく継続的に行うことができます。
また、「シンMMT2050」が持つ国内供給力の強化や特定の財に限定した戦略的価格統制といったインフレ対策は、エネルギーや食料などの戦略物資に関するコストプッシュ・インフレのリスクを抑制し、国民生活の安心を直接的に守る上で不可欠です。
これは、次の理念テーマである「シン循環型社会」とも通じる、需要と供給のバランスを適切に形成・保持するための財政支出も対象とします。
この新しい財政基盤は、恒常的なリスクに備える「恒久戦時経済」という視点を、「平時においても安心安全安定が確保される社会経済」「恒常的持続型経済」へと転換させるための、盤石な基盤を提供するのです。
6-2 「シン社会的共通資本2050」の財源・財政基盤としての「シンMMT2050」
「社会的共通資本2050」は、医療、教育、交通・通信などのインフラ、そして自然環境といった、社会の持続性と市民生活の質を支える基盤資源の健全な維持・拡充を目指す理念です。
従来の市場原理や私有化の進展により公共性が弱体化してきたこれらの領域に対し、「シンMMT2050」は新たな解決策を提示します。
「シンMMT2050」の貨幣・財政システムは、これらの「社会的共通資本」の維持・拡充に必要な膨大な財源を安定的に確保し、従来の財政制約に縛られることなく長期的な視点での投資を可能にします。
例えば、老朽化した社会インフラの再生・整備、質の高い医療・教育サービスの全国的な提供、環境保護への大規模な取り組みなど、本来的に市場原理に馴染みにくいが社会全体にとって不可欠な分野への投資も安定的に実現します。
特に、労働生産性の向上を紋切り型に求めにくい介護、医療、保育などのケアサービス分野において、「シンMMT2050」が安定的な財源を供給することで、これらの分野の人材不足を解消し、質の高いサービスを維持・発展させる方策を示します。
これは、それらの分野の仕事が公共性を強く持ち、これにより、全ての市民が安心して暮らせる社会の基盤が強化され、「社会的共通資本」の「保護」と「補完」が実現されるためでもあります。
6-3 「シン循環型社会2050」の財源・財政基盤としての「シンMMT2050」
「シン循環型社会2050」は、資源・エネルギー・経済・人材の流れを一方向から循環へと再構成する社会モデルです。
「シン安保2050」が掲げる「安定」や「保全」は、地球環境や資源循環が前提条件として成立することから、この理念は日本社会の持続可能性の根幹をなします。
一つの明確な方針としては自国内「自給自足」可能社会の実現を意味するということができます。
「シンMMT2050」は、この循環型社会への移行に必要な大規模な初期投資と継続的な財源を強力に支援します。
具体的には、食料自給率の大幅な向上、気候変動に伴う農林・畜産・水産業の新しい持続モデルの研究・構築、再生可能エネルギ・グリーン水素エネルギー化への転換、廃棄物ゼロ社会の実現に向けた技術開発やインフラ整備、地域内での資源循環を促すモデル事業、エコツーリズムの振興など、従来の財政支出では実現困難だった取り組みを可能にします。
さらに、「シンMMT2050」が持つ持続的な財政支出の機能は、長らく日本を苦しめてきたデフレ圧力を克服し、経済を活性化させると同時に、環境投資を加速させることで「グリーン経済」への転換を促進する可能性を秘めています。
但し、これらが従来型のMMTの主目的であったこととは、かなり異次元の包摂的戦略的理念であることは、ご理解頂けたことと思います。
この財政基盤が、資源の自給自足化や、あらゆる「断絶」を再び結びつける「補完」的思考を支え、「循環型社会2050」の実現を加速させます。
なお、シンMMTを、シン循環型貨幣と言い換えて論じたことでも、シン循環型社会との親和性が強いことが分かると思います
6-4 「シン・イノベーション2050」の財源・財政基盤としてのシンMMT2050
「シン・イノベーション2050」は、単なる技術革新の推進を超え、AI、ロボティクス、バイオテクノロジーなどの先端技術を社会の安定と共生にいかに活かすかという価値観の変革を目指します。
また「シン・イノベーション」が及ぼす、あるいはもたらすベネフィット、メリットが、従来のITが主眼としての生産性向上や効率向上一辺倒ではない、他領域、多様な領域での成果創出・発展にも及ぶことを要件とすることをお伝えしておきます。
その具体的な考え方と内容などについては、次に予定の「シン・イノベーション」記事で展開できればと考えています。
技術は社会の「保」を強化する手段であると同時に、「リスク(不安)」の源ともなり得るため、その健全な発展には強固な基盤が不可欠です。
「シンMMT2050」は、未来の成長を牽引するイノベーション分野への大規模かつ継続的な研究開発投資を支えます。
最先端科学技術、AI、ロボティクス、宇宙開発など、短期的な収益性にとらわれず、長期的視点での先述したように、従来と異なる、広範な国家戦略的・政策的投資領域にも踏み出すことになるでしょう。日本の種々の領域での技術競争力・技術開発力を高め、経済と社会全体のレジリエンス(弾力性・回復力)を強化します。
また、イノベーションを担う人材の育成、そして新しいアイデアを持つ起業家やスタートアップ企業への資金供給を、「シンMMT2050」がどのように後押しするかを具体的に提案しています。
これにより、多様な才能が挑戦できる社会の基盤を築き、技術革新が倫理的規範や制度的「補償」と両立しながら、社会全体の「安心」を高め、持続可能な発展に貢献する「安定基盤」の構築を促進します。
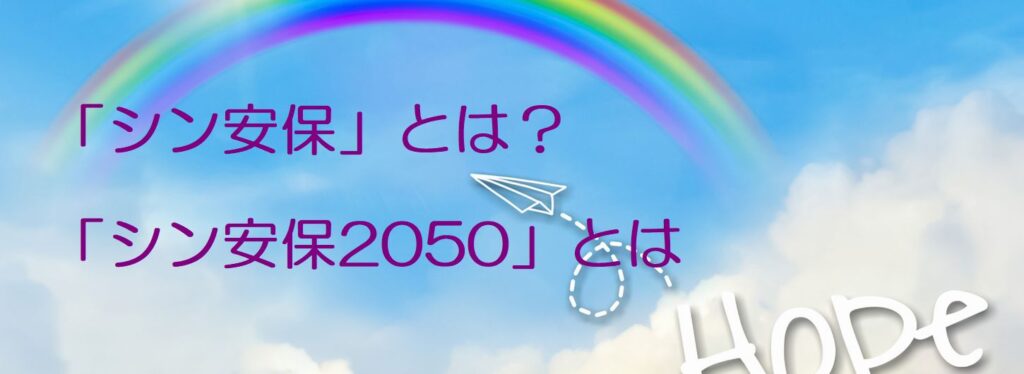
第7節 シンMMT2050の実現への課題と道筋
ここまで、「シンMMT2050」の理念化のための考察と確認を進めて来ました。
シン安保2050、シン社会的共通資本2050、そしてシン循環型社会2050との関係性と包摂性も確認しました。
それ故に、理念の、現実での具体化とそのための方策・道筋造りは、これからの課題でもあります。
以下、その主な命題だけメモ書きし、これからの取り組み作業のための確認事項としておきたいと思います。
7-1 課題1:シンMMT2050の財政支出事業の運用基準と法制整備
・適用対象事業領域の整理
・年間予算化と運用・適用基準作り
・「シンMMT2050法」(仮称)の作成・提案
7-2 課題2:シンMMT2050のマネジメント及びガバナンス基準と管理体制整備
・国家と日本銀行(中央銀行)との新しい関係(責任と権限)の構築
・運用管理のためのシステム及び組織体制の開発と整備(デジタル通貨システム、セキュリティその他)
・国家・地方自治体等公共事業領域の分担化、国家・地方自治の関係・連携制度の整備
・運営管理主管、監理・監査等中立機関整備
・リスク管理システム整備・開発
7-3 課題3:シンMMT2050の政治イシュー化及び立法化・行政化プログラム
・「シンMMT2050」政策化政党開拓と主管政党明確化
・立法化戦略形成
・行政システム移管計画立案
7-4 課題4:シンMMT2050の理念・法制・実現シナリオ等情宣活動と合意・同意形成計画
・市民・国民に理解を得るためのPR活動計画立案と実行
・同意・賛同者の組織化と組織拡大行動計画と実行
7-5 課題5:シンMMT2050実現のための対外的活動及びスケジュール管理
・海外関係機関との事前説明と問題対策検討(外為対策、IMF対策他)
・各国への説明と必要交渉
・シンMMT2050実現のための中長期計画化・スケジューリング
まとめ
本稿「シンMMT2050」では、現代貨幣理論(MMT)の基本概念とその限界を深く考察し、来るべき2050年の日本社会構想における新たな財政・貨幣システムの在り方を提示しました。
私たちは、従来のMMTが持つ課題、特に財政規律やインフレリスク、政治的実装の困難さといった批判を直視しました。その上で、日本社会の固有の状況と未来のビジョンに合致するよう、MMTを「シン」の概念へと昇華させる必要性を強調しました。
「シンMMT2050」は、単なる経済成長や景気刺激を目的とするものではありません。
むしろ、国(家)社会が国民との「シン社会契約」に基づき、貨幣創造権を規律ある形で活用し、「シン循環貨幣MMT」という新たなシステムを通じて、国民の「安心安全安定・保持保有確保(安保)」と「ウェルビーイング」を最大化するための「公共的資本」への戦略的投資を可能にするものです。
これは、従来の財政規律主義からの脱却を図り、実体経済に即した「機能的規律」を追求します。そして、特定目的の**専用デジタル通貨(PUDC)**の活用により、貨幣の循環と回収・消却メカニズムを組み込み、インフレ抑制と国内供給力強化を図りながら、「公益・公共民主主義」を追求するものです。
「シンMMT2050」は、「シン安保2050」「シン社会的共通資本2050」といった先行する理念だけでなく、今後議論する「シン循環型社会2050」「シン・イノベーション2050」の実現を支える、不可欠な財源・財政基盤となります。
この包括的な連携を通じて、私たちは、格差が是正され、個人の尊厳が守られ、誰もが豊かな未来に希望を持てる「共生の近未来」へと日本社会を導く羅針盤を築き上げていくことができるでしょう。
次章では、この「シンMMT2050」の財政基盤を活用し、資源・エネルギー・経済・人材の流れを再構成する「シン循環型社会2050」について、具体的な考察を進めていきます。どうぞご期待ください。