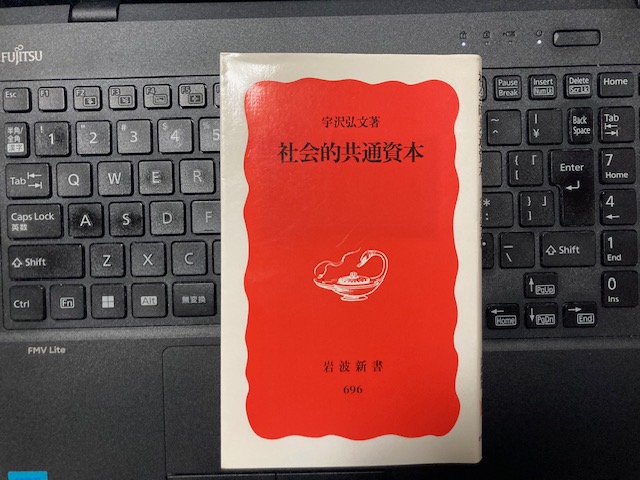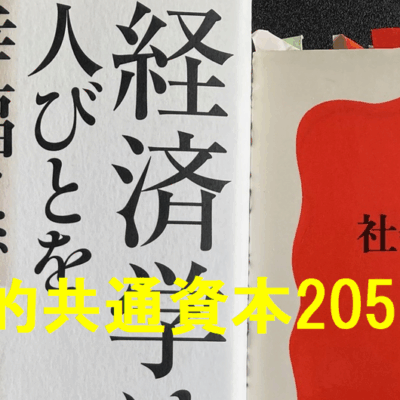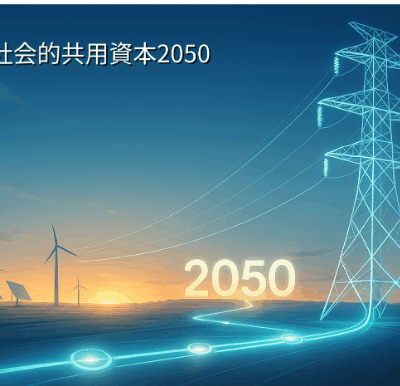社会的共通資本とは何か|宇沢弘文の思想と「もうひとつの資本主義」
はじめに:2050年に向けた社会の基盤とは
「2050年の望ましい日本社会の創造」を掲げる当サイト【ONOLOGUE2050】では、単なる制度改革や技術革新だけでなく、社会の根幹をなす理念的支柱を設定すること重視しています。
その最初の一歩として取り上げるのが、経済学者・宇沢弘文氏が提唱した「社会的共通資本(Social Common Capital)」の考え方です。
現代の資本主義社会が陥りがちな「貨幣的利潤追求の論理」に対し、「社会的共通資本」は、公共性・倫理・持続性を軸にした“もうひとつの資本主義”の可能性を示していると考えています。
本稿では、その基本的な意味と構造、関連する社会領域との接点、そして今後の日本社会における位置づけについて掘り下げていきます。
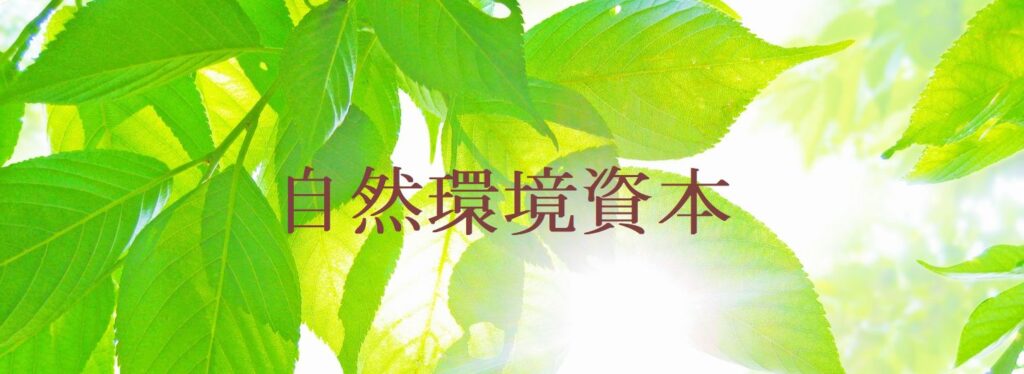
社会的共通資本とは何か
社会的共通資本とは、すべての人が安全かつ人間的な生活を送るために必要不可欠な社会の基盤資源であり、私的利益ではなく公共的価値によって管理・維持されるべきものです。
この概念は、1970年代から宇沢弘文氏によって展開され、市場原理では制御しきれない領域において、倫理と公共性の原理を取り戻すための理論的枠組みとして注目されてきました。
特に重要なのは、「社会的共通資本」は単に道路や上下水道といったインフラだけでなく、制度・文化・自然環境に至る広範な領域を対象としている点です。
私が宇沢氏のこの考えを知り、興味関心をもったきっかけは、「ベーシックインカム」について深く考察する機会を得たことからでした。
ベーシックインカムが、制度として、そして文化として、社会的共通資本の一種である。
日本独自のベーシックインカム、ベーシックペンションを提唱する所以です。
(参考) ⇒ https://basicpension.jp
ベーシックペンションについては、リンク先サイトを見て頂ければと思います。
また、今後の当サイトの中でも頻繁に触れる機会があると思います。
社会的共通資本の分類と構成要素
以下は、宇沢氏の定義に基づく、社会的共通資本の主要な分類とその特徴です。
| 分類 | 具体例 | 役割・特徴 |
|---|---|---|
| 自然環境資本 | 森林、河川、大気、海洋など | 生命維持に不可欠な生態系。過度な開発や私有化から守るべき「共の財」。 |
| 社会インフラ資本 | 道路、上下水道、電力・通信、公共交通 | 日常生活の基盤を成す設備群。経済効率ではなく、地域平等性が重視される。 |
| 制度的資本 | 教育制度、医療制度、司法、行政、金融システム | 社会の公正性・持続性を支える制度。市場からの独立性と専門性が鍵。 |
| 文化的・知的資本 | 学術知、文化遺産、言語、報道、芸術 | 精神的・文化的生活を支える土壌。代替不可能な人類共有の財産。 |
これらは本来、単独ではなく相互に支え合う構造を持っており、特定の領域が毀損すれば、他の領域にも深刻な影響を及ぼします。

当サイトの関連カテゴリーとの接点
社会的共通資本の考え方は、当サイトで扱う以下の各カテゴリー・サブカテゴリーとも密接に関わります。
1)Resources(エネルギー、公共インフラ、国土・土地、希少資源、環境、食料等):
社会的共通資本の根幹をなす自然資本やインフラ資本が集中する領域であり、持続可能な管理と保全の理念と直結します。
2)Economy(労働・雇用、産業経済、社会経済、経営・マネジメント、金融・資本、地域・公共経済等):
経済活動が公共的価値とどのように調和するかを問う文脈で、「金融資本主義」との対比や「倫理的経済」の基盤として社会的共通資本が機能します。
3)Politics(安全保障、政治・行政、立法・司法・憲法、財政等):
国家による制度管理、市民参加、公共予算配分の在り方など、共通資本の設計と運営に不可欠な統治構造の視点と重なります。
4)Social System(地域・地方・都市、社会保障、教育制度等):
教育・医療・福祉といった制度的資本の適正な構築と運用が求められる領域であり、地方分権や地域共生社会との関係も含め再評価されるべき分野です。
5)Social Issues(高齢化社会、少子化社会、格差社会、ジェンダー、事件・犯罪等):
社会的共通資本の劣化や喪失が引き起こす問題群。公共性・包摂性の回復を通じた持続可能な社会への転換が求められます。
6)Global Society(国際問題、国際関係、気候変動・地球環境):
気候変動・海洋汚染・パンデミックといったグローバル課題に対し、国家を超えた「地球規模の社会的共通資本」の視点が重要となります。
社会的共通資本 vs. 金融貨幣資本
現代の資本主義は、「貨幣的利潤の最大化」を価値判断の中心に据えてきました。人間の生活環境や文化、公共サービスでさえ「市場化」され、効率性と収益性が優先されるようになっています。
しかし社会的共通資本は、この潮流に対抗する「もうひとつの資本主義」の軸足を提供しています。
| 観点 | 社会的共通資本 | 金融貨幣資本 |
| 目的 | 人間の尊厳と生活の質の保障 | 利潤の最大化と資本の蓄積 |
| 評価基準 | 公共性、持続性、倫理性 | 効率性、収益性、市場価値 |
| 管理主体 | 公的機関、専門家、市民 | 企業、投資家、金融機関 |
| 時間軸 | 長期視点(世代を超える) | 短期利益(四半期・年度) |
宇沢氏の思想が提示するのは、貨幣の論理では測れない人間的・社会的価値を重視した経済観であり、これを実現するためには社会的共通資本の再構築が必要不可欠です。

宇沢弘文氏の「社会的共通資本」と財政問題について
とは言っても、社会的共通資本の維持と発展には、当然ながら持続可能な財政的裏付けが不可欠です。
しかしながら、宇沢氏の論考においては、制度の設計や公共性の倫理的意義については詳述されている一方で、それを支える財政的な具体方策――例えば、税制の見直し、再分配の仕組み、財政優先順位の改革など――には十分に踏み込まれていないという特徴があります。
私が高く評価し、尊敬している宇沢氏ですが、この点には不満感を持っています。
氏は、医療や教育などを「制度資本」として位置づけ、その公平性と専門性を守るべきだと述べています。しかし、それに要する財源の確保方法については「公共の責任」として抽象的に触れるにとどまり、制度化のための政治的・実務的道筋は描かれていません。
(参考)
⇒ ヒルサイドライブラリー・講演記録:https://hillsideterrace.com/series/10184/
したがって、この点は今後、私たちが「社会的共通資本」を実際の社会政策に反映させるうえで避けて通れない課題です。
当サイトでも、今後「財政」や「制度設計」に関連して、具体的な評価や提案に踏み込む必要があると考えています。

「現代の市場経済が抱える課題」とは何か? そして対抗軸としての意味
なお、宇沢氏が「社会的共通資本」を提起した背景には、現代の市場経済が抱える深刻な問題群への強い懸念がありました。
以下に、その主な課題を整理します。
| 市場経済の課題 | 説明 |
| 利潤至上主義 | 金融市場や大企業が短期的な利益を優先し、社会的・環境的な価値を犠牲にしている。 |
| 公共性の喪失 | 医療や教育など、本来は公共の領域が市場に明け渡され、格差が拡大。 |
| 外部不経済の増大 | 環境破壊、公害、都市の過密・過疎化など、社会的コストが無視される傾向。 |
| 倫理の喪失 | 経済合理性がすべてに優先し、倫理や人間性が軽視される構造。 |
| 世代間不平等 | 現在の豊かさが将来世代の負担によって支えられている。 |
これらの課題に対して、社会的共通資本は“対抗軸”として構想されます。
つまり、「収益性」ではなく「人間の尊厳と共生」を軸とする社会構想としての資本主義です。
このような意味で、社会的共通資本は単なる公共インフラの話ではなく、社会の構造的再設計と倫理的再定義の提案であり、政策・教育・経済・行政の全分野に波及すべき価値原理の提唱だといえます。
しかし、繰り返しになりますが、このような一般的な帰結方法には、当然限界があります。
その理由は、現在の社会政策や財政問題など、政治的社会的そして当然経済的な観点での問題が山積していることで示されています。

社会的共通資本管理のあり方と「専門性」と「市民性」、そして「政治性」への視座
以上述べてきたように、社会的共通資本は、その重要性ゆえに単に「公共のもの」として認識され、かつ存在するだけでは、十分に機能するとは言えません。
宇沢弘文氏は、これらの資本は高度な専門知識と倫理的責任感をもって丁寧に管理されるべきだと強調しています。
同時に、市民一人ひとりの関与と民主的な意思決定プロセスの確保も不可欠です。つまり、専門性と市民性の両立が求められるわけです。
しかし、こうした「市民性」も、単なる参加や声の表明にとどまっていては、その理念が具体的な社会制度に反映されることは困難です。
そこには、最終的に「政治」の力が必要になります。
つまり、社会的共通資本の理念を社会全体に浸透させ、政策として実現していくには、それを支える政治的基盤、すなわち、制度や法の枠組み、そしてその担い手となる政治的主体、政党の存在が不可欠です。
もちろん、国政レベルでのことです。
これが、最も私が主張したい点です。
将来的には、新たな政治的組織やネットワークが、市民性のなかから育まれ、公共的価値を軸にした政治の担い手として機能していくことが求められます。しかし今はそれを見通すことができませんし、当分不可能にも思えます。
その前提をもっても、今はまず「社会的共通資本」という考え方をより多くの方々と、そしてこれからの政治を担う人々に広めていくことが第一歩になります。
価値を共有し、議論を積み重ね、やがて政策へと結びつける。
2050年をも見据えて、その長いプロセスの出発点に、今、立っていると考えたいと思います。

おわりに:理念としての「社会的共通資本」の位置づけ
社会的共通資本は、単なる制度設計論ではありません。それは、「どのような社会を目指すのか」という理念そのものです。
2050年の望ましい日本社会とは、どういうものかを、どうあるべきか。
その内容やあり方を考察し、提案していくことが当サイトの目的です。
その中で、宇沢氏の「社会的共通資本」の考えを、基盤として活用し、十分に反映させていきたいと考えています。
しかし、金融貨幣資本が優位性を保つこと、政治システムが機能していないことなど、その実現の壁になっている現実があります。
その実現のためには、「もうひとつの資本主義」としての社会的共通資本を見つめ直し、制度・教育・政治・経済のすべての領域で再設計・再構築していくべきとも考えています。
これから、メインカテゴリーである【Onologue2050】において、他の個別のカテゴリーに関する論考・記事作成を進めていきます。
その取り組みにおける中心軸となる「Philosophy理念」として「社会的共通資本」を位置付けていることをお知らせするのが本稿の目的でした。
「Philosophy理念」として位置付けたい事項が他にもあります。
順次、あるいは、必要に応じ、それらについてお伝えしていきたいと考えています。
ただ、理念的なことばかりテーマとして論じていては、宇沢氏批判に矛盾します。
できるだけ、今・現在の諸課題を取り上げながら、社会的共通資本として論じたり、他の理念を活用して論じるなど、展開していきます。
どうぞこれから宜しくお願いします。
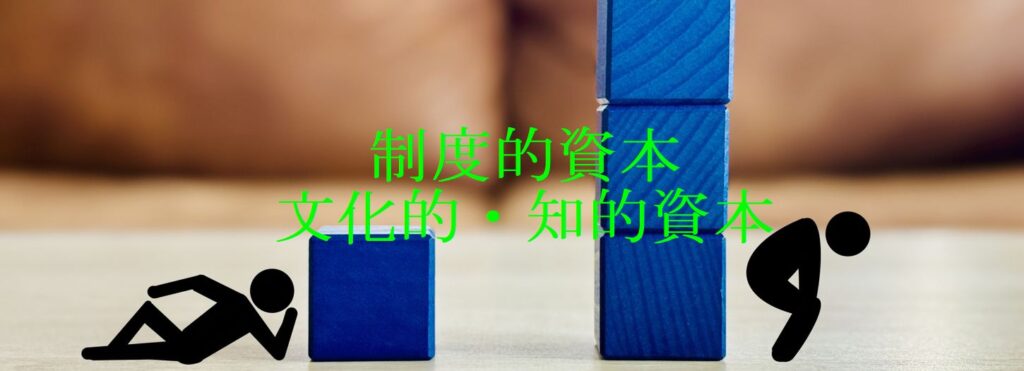
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(出典・参考文献)
・宇沢弘文『社会的共通資本』(岩波新書、2000年)
・宇沢弘文『経済学は人びとを幸福にできるか』(新潮選書、2006年)
・鈴木壽一「宇沢弘文と現代社会への視座」『社会倫理研究 第31号』(南山大学社会倫理研究所、2022年)
https://rci.nanzan-u.ac.jp/ISE/ja/publication/se31/31-17suzuki.pdf
・HILLSIDE LIBRARY 宇沢弘文関連講演記録
https://hillsideterrace.com/series/10184/